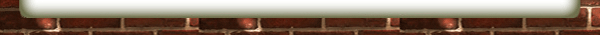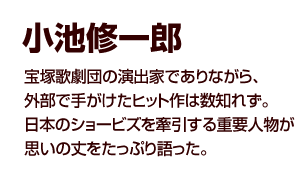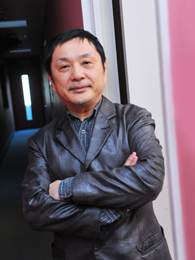
――その長い歴史の中では、どんな観客が多かったのですか?
「関西も東京もそうですが、子供の頃、母親に連れられて観てファンになって通い、その間に学校に行ったり就職したり結婚したりして、暫く来なかったりするんですよ。でも最終的に、ある年齢になるとすべての煩悩を捨て去って(笑)、宝塚に行こうとなる。それが有難いお客様で、ある程度お金も時間も持っている方たちが連れだって来るという、ビジネスモデルとしても最高のパターンだったと思うのですが、これが崩壊しつつあるんですね。今は、ひとりでキャリアウーマンとして働いていらした方が、落ち着いた年齢になってから来てくださる例も多いですが、娘を巻き込んで来るという人数の掛け算は期待できないわけですよね。それと、昔は劇場の近くにぶらっと来ると、誰か顔見知りがいて、“チケットが1枚あるんだけど、観ません?”といった、転売のネットワークが見事に広がっていたんですよ。宝塚友達って、どこに勤めているか、どこに住んでいるかは知らないのに、“誰々のファンの何とかさん”で、口コミならぬ顔コミと言うか、顔見知りのコミュニティがあって、その繋がりがすごく多かったんですね。でも、経済状況や人間関係の形も変わってきて、淘汰されてしまった。無論今はネットという便利な媒介はあるのですが、必ずしも機能しているとは言えないようです。宝塚ファンの在り方と社会構造はリンクしていて、再来年に100周年を控え、今後どうやって社会と結びついて運営していくかが、大きな課題だと思います」
――今後はどうなっていくのでしょう?
「母親から娘へ伝わっていった物が途切れ、ある年齢からは、母親でさえジャニーズの方が好きだったりしますから、そうするともう、宝塚はノスタルジーと言うか、心のよりどころではなくなってしまうわけです。その代わり、少女時代に宝塚体験がない人がある程度の大人になってからはまって下さったり、またこれがすごいんですが(笑)、そういう大切な客層が存在する一方で、今度は若い男優を舞台に出して女性を集客するようになった(笑)。日本の演劇文化が、東宝から新感線や地球ゴージャスに至るまで、女性客相手に男性が演じるビジネスになってしまったんです。お笑いに至るまで全部そうですよね。映画のプロデューサーから、やっぱり女性が見に来ない映画はダメだと言われました。アクションだろうが時代劇だろうが、もう男性向け映画のスターは成立しない。特に主婦に人気が出ないとダメだそうです。今や女性が選択権を持っていて、消費構造の中でライバルが増えすぎて、その中で宝塚が生き延びていくのは大変だと思います。一方では性の解放と言うか、男女雇用機会均等法もあって、女性たちが、結婚を前提とした恋愛という昔のモラルに縛られなくなった。もうじき日本もフランスのように、少子化対策で未婚の母を奨励する時代が来るかもしれない。別に結婚なんかしなくてもいいと。育児の保証がなされて女性たちが働くことができれば、子供も産める。“産めよ、増やせよ”のニュー・バージョンですね。そんな中で、現実にありえない恋愛の夢、恋愛のファンタジーに浸れる宝塚は、昔とは別の意味で、社会生活に疲れている女性たちの癒しになっていると思います」
――現在、宝塚が抱える一番の課題は?
「社会の成り立ちが変わった中で、これから宝塚はどうしていくかですが、一番難しいのは、既に90年代から言われていた“擬古典化”という問題です。つまり、100年近い歴史の中で、本来はその時代のスターなり演出家なりが、スタッフやプロデューサーたちも含めて、毎回スタイルを作っていたはずなんですよ。またこの擬古典化が微妙で、昔演った演目をそのまま完璧に再現してみせれば、評価が上がって行くのかどうか? 歌舞伎ならいざ知らず、宝塚は短期間で生徒が入れ替わっていくので、ひとつの芸を受け継いで完成させるという世襲のようにはならないんですね。だったらその時代の生徒たちとスタッフたちで、新しい価値観を作っていけばいいと思うんだけど、そこにいくつか手本と言うか、ひな形があるんです。それに対して、どうやっていくかということですが、40年前に始まった “ベルばら期”はまだ続いていますから、その中で擬古典化しかけている部分もある。自分自身の仕事なんだから、部外者みたいに言ってはいけないんだけど、もっとこれが21世紀の宝塚だと感じさせる、演目やスターが出て来ていいんじゃないかなと思います。極端に、観たこともないようなものではなくて、宝塚だけど、これは新しいかなと思えるものが出て来たらいいですね。私なんか20世紀の人間で、入団して35年ぐらい経ってしまったので、平成になって入ってきたような演出家や、平成生まれの生徒もいるぐらいですから、彼らが何か次の物を出してくれるといいなあと思いますね」
――それでも、今までミュージカルと言えば、多くの人が、ブロードウェイとウェストエンドだけだと思っていた日本に、小池先生が『エリザベート』や『ロミオとジュリエット』など、ウィーンやパリのミュージカルを定着させた功績は大きいと思います。
「いや、それは宝塚という所のキャパシティの広さだと思いますね。それと、ヨーロッパの物が、『レ・ミゼラブル』や『オペラ座の怪人』のようなオペラ形式で、ことにパリのものは演劇性より、スペクタキュラスな見せ方をすることに意を注いだ演目が多く、そこが宝塚に合っていたんだと思います。ブロードウェイの物は、どうしても予算が減っていって、よく言えば中身に集中していると言うか。よく言われるように、英語の表現をメロディに乗せるテクニックの競技のようなことが、あるわけです。しかし、翻訳して世界の人たちが共有して楽しめるかと言うと、そうではない。それにテーマも、今のアメリカ人、殊にニューヨークの人たちは大変喜ぶけれど、やっぱりグローバルな異国の人間が魅力を感じるかと言うと、ちょっと難しい物が多いですよね。例えばトニー賞を取った『ブック・オブ・モルモン』は、アフリカでモルモン教を広める話でしょ? その辺の微妙さが、広くあまねく日本で受け入れられるのはなかなか難しいのではないかと思います。全世界で当てたいなら、プロデューサーたちは普遍性のあり方をどこに求めるか、もっと考えなくてはならないでしょう。音楽も題材も。それより私は、韓国のミュージカルを観るとオリジナルの作品がすごくよくて、これは本当に悔しいですね。『光化門恋歌』と『ソビョンジェ(西便制)』という作品なんて素晴らしかったですよ。『光化門恋歌』は明治座で来年演るそうですけど。昔のポップスになぞらえて、学生運動をやっていた若者の後日談ですが、ストーリーも面白いし、音楽がよくて歌がうまい。数年前まではビジュアル面が、洗練されていない印象がありましたけど、美術や映像衣裳の色彩感覚も見事で、負けたという感じです」
――お話を伺っていると、男女キャストの『エリザベート』や『ロミオとジュリエット』は、宝塚というフォーマットを経由したからこそ、成立しているという感じがします。
「そうですね。本当に面白い結果になったと思います。韓国版『エリザベート』は、プレビューでトートのかつらが犬夜叉に似てると不評だったそうで(笑)、全員地毛を染めて演ってましたけど、歌も上手いし、モデルみたいにイケメンの俳優でも、普通の若いお兄さんが、コスプレの人たちの中に紛れ込んでるみたいで、やや存在感が薄いような気がしました。オランダ版は、中南米系に見える、浅黒い肌で短く黒い髪のトートが登場しますけど、現代のその辺にいる人に見えるんですよ。東宝版は、宝塚を経由したこともありますけど、初演当時はビジュアル系バンド・ブームの直後で、その影響もあるかもしれません。それに、クンツェさんの原台本には、ロックスターのようなアンドロギュヌスだと書かれていて、デビッド・ボウイやフレディ・マーキュリーのイメージだと感じたので、その要素は残さないとつまらないと思ったんです」
――小池ファミリーと言うか、クンツェさん、シルベスター・リーヴァイさん、それにフランク・ワイルドホーンさん、プレスギュルヴィックさんと、小池先生は、単なるオリジナル・スタッフと翻訳版演出家という関係を超えた、強い絆で結ばれているように思えます。
「最初宝塚で上演する時は、皆さん、いったいどうなるんだろうと興味を持ってくださって、大変なアドバンテージでした。その上に演らせていただいた作品がうまく行ったので、多少はご信用いただけたかなとは思います。でも、私はあくまで、宝塚という女性が男性を演じる大変特殊な場で、別の株を持ってきて栽培している職人みたいなものなんですよ(笑)。この苗床に入れると、“バラが牡丹になっちゃいました”みたいな(笑)、そういうことをやっているんです。料理で言えば、宝塚はお菓子なので、ハンガリーのグラーシュっていうビーフシチューでも、お菓子にしなきゃいけない(笑)。同時に、宝塚という文化、様式と言うなら様式ですが、その宝塚のスタイルに当てはめることで、ちょっと違う味付け、処理がなされて、作品の価値観が変わるわけです。宝塚は絶対的なヒロイズムの世界なので、主役がはっきりすること、もうひとつは、物語を女性だけで演じることで、人間の体臭のように消されてしまう部分がある反面、これは何を言っているのかとか、どこが問題なのか、この人たちの関係性はどうなのかという部分は抽出されて残る。従ってドラマの根幹が結晶として出て来ると思うんです。男女優バージョンは、よく言えば、役者の重みや厚み、若者のエネルギー、いろんな物が出て来るので、その面白さはあります。ただ、ドラマの純度は、逆に宝塚の方が出て来ると思うんですよね。最後にはそれしか見る物がなくなって、筋が見えてくる。『ハウ・トゥ・サクシード』(梅田コマ劇場、2000年)の時に男女のバージョンより宝塚の方が面白いと言われたのは、オジサンの役を若い女の子たちが演っているから、当然作らないとできません。その結果、筋や人間関係のあり方が強調されて行くので、成立していく。女性だけという制約は、実は宝塚の大変な強みであり、魅力につながっていると思います」

――今後外部でやりたいことは?
「やりたいことはあり過ぎて困るくらい。日本のミュージカルは、役者も観客も宝塚と劇団四季がベースで、東宝ミュージカルにもいろいろな人が参加して、ある程度間口を持っていると思います。しかし、韓国のすごさに対しては、ここまで引けを取ったかってちょっと悔しいところがあるんですね。結局は基礎的な歌唱力が違うので、出て来たばかりの人でも、十分聴かせられる歌を歌っている。そこで差がつくのだと思います。と言うのは、近年の殊に翻訳ミュージカルは、音域が広くて歌が難しいから、なかなか“ちょっと僕もCD出してます”みたいな俳優や、1曲2曲ヒットがあるぐらいの若い歌手にはかなり厳しいんです。結局、レッスンに労力を要することになって、しかも、そんなに儲からないかもしれないし、メディアで注目を浴びるかどうかもわからない。昔はミュージカル出演と言うと大変話題になりましたけど、東宝でも年に1、2本しかないような時代の話、今のように作品が氾濫していたらあまり話題にならないし、日本の中でトレンディな文化じゃなくなってしまった。大変いい人材が興味を持ってくださって、そこにお客様が集まるようにならないと、活性化していかないと思います。東宝生え抜きのミュージカルのプロ、井上(芳雄)君のような人がいっぱい出てくれたらいいですよね。そうすれば、もっともっと面白いことができるし、予算も組めて、いい企画がいっぱい出るでしょう。そうなることを祈ります」
Text●原田順子 Photo●源賀津己
こいけ・しゅういちろう 1955年生まれ、東京都出身。1977年、宝塚歌劇団入団。1986年、バウホール公演『ヴァレンチノ』の作・演出でデビュー。1996年、ウィーン発のミュージカル『エリザベート』の日本初演にあたり、潤色・訳詞・演出を担当。ほかの主な演出作品に、『華麗なるギャツビー』『PUCK』『NEVER SAY GOODBYE』『THE SCARLET PIMPERNEL』『カサブランカ』(以上宝塚歌劇団)、『モーツァルト!』『キャバレー』『MISTSUKO〜愛は国境を越えて〜』『ロミオとジュリエット』(以上外部公演)など。菊田一夫演劇賞、千田是也賞、読売演劇賞など受賞多数。
『エリザベート』
5月9日(水)〜6月27日(水) 帝国劇場(東京)
7月5日(木)〜26日(木) 博多座(福岡)
8月3日(金)〜26日(日) 中日劇場(愛知)
9月1日(土)〜28(金) 梅田芸術劇場 メインホール(大阪)
宝塚歌劇月組『ロミオとジュリエット』
6月22日(金)〜7月23日(月) 宝塚大劇場(兵庫)
8月10日(金)〜9月9日(日) 東京宝塚劇場(東京)
宝塚歌劇宙組『銀河英雄伝説@TAKARAZUKA』
8月31日(金)〜10月8日(月) 宝塚大劇場(兵庫)
10月19日(金)〜11月18日(日) 東京宝塚劇場(東京)
※宝塚大劇場公演は7/28(土)一般発売、東京宝塚劇場公演は9/9(日)一般発売