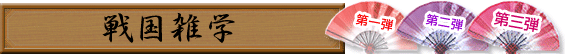@ぴあTOP > 特集 > 戦国武将特集 > 戦国雑学
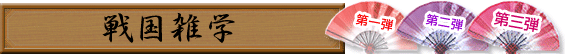
ふ〜ん度 ★
短足のため、馬に乗れなかった武将
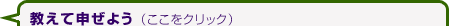
極端な短足だったという今川義元。馬に乗ることができず、常に輿で移動していたと言われている。また、他にも幼少時に馬から落ちてケガをしたため、馬を恐れるようになったという、説もある。

ふ〜ん度 ★★
伊達政宗の暗殺を企てた女
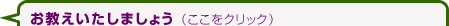
幼い頃天然痘をわずらって右目を失明した伊達政宗を嫌い、弟の小次郎を溺愛したといわれる生母・義姫。父である輝宗が畠山義継に拉致された際、政宗は容赦なく鉄砲を放ち、輝宗は死んでしまう。このことから、義姫は政宗を疑いだす。さらに義姫の一族である最上家に攻め入ったことで、ますます不信感を募らせる。そして、義姫は政宗の膳に毒を盛り暗殺を謀る。しかし、これを事前に見破った政宗は、刃を母・義姫に向けるが、かばった弟・小次郎を斬殺してしまったという。戦場に乗り込んでいくほどの気丈な女性で、“奥羽の鬼姫”と呼ばれた義姫だったが、晩年は政宗と完全に和解していたとみられる。

ふ〜ん度 ★★★
細川ガラシャの遺品、ロザリオに描かれていた模様
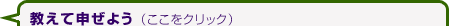
明智光秀の娘で、細川忠興に嫁いだ細川ガラシャ。光秀は本能寺の変で謀反を起こし、謀反人の娘となったガラシャを石田三成は人質としてとろうとしたが、ガラシャはこれを拒否し、家老に槍で部屋の外から胸を貫かせて非業の死を遂げた。残された遺品のひとつに、深く信仰していたというキリスト教のロザリオがあり、模様は明智家の家紋である桔梗紋だったという。

ページTOPへ
ふ〜ん度 ★
前田利家のあだ名は?
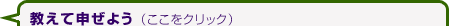
加賀100万石の大大名・前田利家。武骨者で派手な身なりだったため、“かぶき者(傾奇者)”というあだ名で呼ばれていた。利家のほかにも、長宗我部国親の“野の虎”、加藤清正の“鬼将軍”、伊達政宗の“独眼流”などのあだ名も有名。

ふ〜ん度 ★★
豊臣秀吉が認めた、絶妙な“気配り”武将
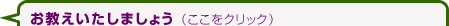
近江を訪れた豊臣秀吉がのどが非常に渇き、ある寺で茶を所望した。そこは、石田三成が小僧をしていた寺だった。三成は秀吉に1杯目にぬるい茶、2杯目に少し熱めの茶、3杯目には熱い茶を出した。その絶妙な気配りを高く評価した秀吉は、寺に申し入れ、三成を臣下として迎え入れたのだった。

ふ〜ん度 ★★★
前田利家がまんまと引っ掛かったいたずら
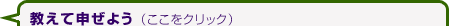
前田利益(慶次)は、文武両道だったが、奇行が目立つかぶき者として知られる。義理の叔父にあたる利家とはうまがあわなかったといわれ、前田家を出奔している。その際、利益は利家を自宅に招く、この時代、一級のもてなしとされていた風呂を利家にすすめる。着物を脱ぎ、風呂に入ろうとした利家だったが、湯船に張られていたのは湯ではなく、冷たい水だったのだ。急いで利益を探した利家だったが、すでに利益は利家の愛馬“松風”に乗って走り去ったという。

ページTOPへ
ふ〜ん度 ★
織田信長が明智光秀につけたあだ名
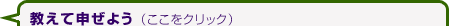
豊臣秀吉を“サル”と呼んだという有名な話があるが、家臣をあだ名で呼ぶことが少なくなかった織田信長。明智光秀にも金柑のようにツルツルしている頭という意味の“キンカ頭”とあだ名をつけていた。実際、光秀の頭髪は薄かったようだが、そう呼ばれて気分がいいはずはない。これが信長に恨みをいだくようになった理由のひとつだとも…。

ふ〜ん度 ★★
生涯側室を持たなかった武将
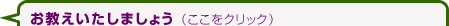
幼くして父を失い、一族は離散し流浪するという苦難を乗り越え武将になった山内一豊。一豊の出世街道は、貧しい生活に耐え、内助の功で夫を支えた妻・千代(見性院)と一緒に開いてきた。嫁入りの持参金で一豊の欲しがっていた名馬を購入し、主君・織田信長に認められた話や、関ヶ原の戦いでは徳川家康についた一豊に、三成挙兵を伝えた「笠の緒の密書」など、良妻エピソードの多い千代。一豊は“出来た嫁”がいたからこそ、側室は必要なかったのかもしれない。

ふ〜ん度 ★★★
戦国時代一の子だくさん武将
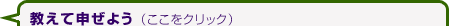
男女合わせて22人の実子と1人の養子がいた織田信長が戦国子だくさんグランプリ。戦国武将は勢力拡大のために必要としたのが女、子どもだった。政略結婚は当たり前の時代。子どもが人質として籠絡手段に使われ、それでも足りないときは、養子をとって相手に送り出したという。

ページTOPへ
戦国雑学 第一弾 第二弾
戦国武将特集TOPへ
特集一覧へ戻る