| ● Round of 16 2006/6/26(17:00) フリッツ・ヴァルター・シュタディオン[カイザースラウテルン] |
|

イタリア |
1 |
TOTAL |
0 |

オーストラリア |
| |
PK |
|
| 0 |
1st |
0 |
| 1 |
2nd |
0 |
| |
ex.1st |
|
| |
ex.2nd |
|
|
|
|
|
|
|
トッティ、カモラネージを控えに回し、デル・ピエロをスタメンで起用。布陣もトニを頂点に4−3−2−1で挑んだイタリアのそんな戦略は、しかしわずか50分で崩壊した。マテラッツィの退場により攻撃サッカーを標榜していたはずのイタリアは、結局守備重視の戦術に変更せざるを得なくなったのだ。
当然ながら、試合はオーストラリアペースで進むことになった。いつゴールが決まってもおかしくはないシーンが目白押しで、イタリアは完全に自陣に引いた。それゆえ、イタリアに決勝点が生まれたのはほとんど奇跡に近い。PKを獲得したグロッソのプレーはもちろん、それを冷静に決めたトッティのゴールは値千金という言葉では足りないほど貴重なものだった。
結局、延長戦に突入するかと思われた試合は、イタリアがロスタイムに得点し勝利をものにしたが、11対10人というハンディマッチの中にも勝敗を分けた別の要因がしっかりと潜んでいた。
|
 |
|
|
ずばり、それはベンチワークだ。リッピとヒディンク。ともに世界的名将の2人だが、この試合で採った戦術は実に対照的だった。
言うまでもなく、交代は3人まで認められているが、それをフルに使ったイタリアに対し、オーストラリアで交代出場した選手はアロイージのみ。つまり、まだ2人選手交代の余裕があったわけで、文字通り余力は十分残していた。ヒディンクの脳裏には、もちろんフレッシュな選手の投入時期についてのプランがしっかりと作成されていたはずで、決勝点を奪われたロスタイムまでそれを行わなかったことを考えると、延長戦で勝負を仕掛けようとしていたに違いない。
一方、リッピは3人の交代をフルに活用している。積極的に選手を入れ替えたからといって評価をしているわけではない。注目すべきは交代出場させた選手だ。マテラッツィの退場の後、10人となったイタリアが最後に切ったカードはトッティだった。この選択こそ、リッピのファインプレーであり、イタリアを救ったと言っていい。
つまり、攻められる時間帯が続き、どうしても後手を踏んでしまいそうな場面でも、リッピは攻めの姿勢を失わなかったのだ。ただ単に守りきるという手段に打って出たのではない。追い込まれていながらも、得点を狙う姿勢を忘れない。その証明がトッティの起用だ。多くの監督がまずディフェンスを固め攻撃を放棄してしまいがちな状況下にあっても、リッピはそんな間違いを犯さなかった。もし、ディフェンスの選手を投入していたならば、さらに攻め込まれる時間が続き、延長の30分間を守れたとは思えない。
追い込まれて“攻めた”リッピに対し、タイミングを計り“待っていた”ヒディンク。ピッチ上ではオーストラリアが攻めイタリアが守っていたが、ベンチワークはその真逆を行っていた。試合内容は平凡ながらサッカーの奥深さをあらためて痛感させられた、そんな名将同士の采配によるゲームだったと言えるだろう。
|
文:佐藤芳記(WORLD SOCCER GRAPHIC取材班) |
|
|
|
 |
|
| LINE UP |
1 ブッフォン 6.5
3 グロッソ 6.5
5 カンナヴァロ 6.0
7 デル・ピエロ 5.5
(10 トッティ/75分 6.0)
8 ガッツーゾ 6.0
9 トニ 5.5
(6 バルザリ/56分 5.5)
11 ジラルディーノ 5.0
(15 イアキンタ/HT 5.5)
19 ザムブロッタ 6.0
20 ペロッタ 5.5
21 ピルロ 5.5
23 マテラッツィ 4.0
|
|
5.5 シュウォーツァー 1
5.0 ニール 2
5.5 ムーア 3
5.5 ケーヒル 4
5.5 クリナ 5
5.5 ヴィドゥーカ 9
6.0 グレッラ 13
5.5 チッパーフィールド 14
6.0 ウィルクシャー 20
5.5 ステリョフスキ 21
(5.5 81分/アロイージ 15)
6.0 ブレッシァーノ 23
|
|
|
|
| トッティ(90+5) |
得点者 |
|
グロッソ(29)
ガッツーゾ(89)
ザムブロッタ(90+1) |
イエローカード |
(23)グレッラ
(49)ケーヒル
(61)ウィルクシャー |
| マテラッツィ(50) |
レッドカード |
|
| 11(6) |
シュート(枠内) |
8(4) |
| 17 |
ファウル |
26 |
| 2 |
CK |
2 |
| 2 |
オフサイド |
2 |
| 41% |
ボール支配率 |
59% |
|
|
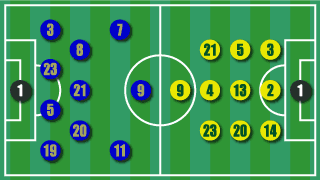 |
|