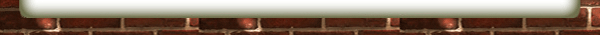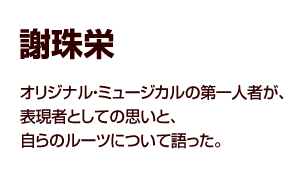――昨今オリジナル・ミュージカルの上演が増えていますが、ともすると粗製濫造になりかねない中で、良質のオリジナル・ミュージカルを作り続けるTSミュージカルファンデーションの占める位置というのは、大きいと思います。
「最近こそ上演が増えましたが、水準の高いオリジナル・ミュージカル作りを目指すより、外国の翻訳ミュージカルを買う方が安心だからという時もあったわけですね。でも、例えばロンドンのボンドストリートを、トムという男が歩いて来るという設定を、外国にも行ったことのない子が、そこら辺の商店街をうろついているような感じで歩いているのは嫌なんですよ。脚本家は自分たちの国の人をイメージして書いてる。やっぱり風土も風習も文化も違う日本で、外国の戯曲をやる必要性があるのかなって、すごく感じるんです。外国の物をやるのなら、その国へ行って空気感もわかって、風土も文化も歴史も知ってから、ちゃんと演じてほしいのに、ホンがいいからというだけでやるのは納得いきません。だから私はオリジナルを創るんです。演劇界にはミュージカルを蔑視する人もいるじゃないですか。それもすごく悔しい。ミュージカルをやっている人たちは技術が必要だから、ものすごく年数もお金もかかります。自分の感性だけで勝負できないことに対しての反感なんでしょうか? でも、演劇の人たちだってこの頃は音楽劇と銘打って歌や踊りを入れるでしょ。どこに違いがあるのかな。もう芝居派、ミュージカル派って柵も取り除かなきゃ。私の力が足りないため、なかなかそこに行きつかないんですけれどね」
――でも、ミュージカルだからこそ伝わってくる物、心に残る物があると思います。
「そうですよね。だから脚本の斎藤君にも、“言葉だけを信用していたらダメ。もっと強烈に音楽が感じさせてくれる物もあるから、言葉だけで全部説明しようと思わないで”と言っています。ただ、踊りがある、音楽があるというだけで満足されても困るので、テーマをいかに伝えられるか、その辺の兼ね合いが難しいんです。脚本家や音楽家、そして私たち演出家が一生懸命勉強して、観客にも納得してもらえる物を作っていきたい。でもスタッフは引く手あまたにはいないので、これからどんどん育っていってほしいです。『ウエストサイド物語』のように、音楽と芝居と歌と踊りが自然に入ってくるエンターテインメントでありながら、ちゃんと演劇的なこともきっちりなされていて、万人が観て楽しかったねというミュージカルを、オリジナルで作らなくてはいけないんです。でも私たちが作れるようになってきたことで、これからもっと出て来ると思います。今は、そのタネを撒いてるところなのではないかなという感じがしますね。この間、久しぶりにNYに行ったのですが、ほとんどがビジネスを感じる舞台。芸術性よりも全てが金次第っていう感じがしました。日本もひょっとしたらそういう形になっていくのではないかなと、実はすごく心配しているところなんです。それはそれとしても、作り手たちが頑張って行かなくてはいけないなと思います」
――オリジナル・ミュージカルがレパートリーとして、何度も再演されるようになるといいですね。
「そうですね。でもそれがなかなか難しくて、すぐに再演すると、ドーンとお客さんが入らなかったりするんですよ。5年ぐらい経っていないとダメなんですね。でも、練って練って練っていい作品になっていく物もあるので、観客の意識を変えないとダメだと思います。演劇界のほうでも、どの作品もほとんど出ている人が一緒で、結局、お客さんが呼べるネームバリューのある人ばかりを使っているんですよね。もっとできる役者さんたちはいっぱいいるのに。でもその点、宝塚と劇団四季が人材がを育てているのはありがたいですね」
――その宝塚のOGの中には、TSで初めて外部作品のことを学んで、その後の飛躍に繋がる人も多いと思いますが。
「後輩たちには、私がやっているということで安心感もあってほしいし、徹底的に舞台を追求していくという姿勢も忘れないでほしいんです。こうしろと強制するわけではなく、どんな舞台作りをしたいかは本人たち任せなので、私の思いを感じてくれる子は、そういう舞台を目指してくれるし、ザ・芸能界に行ってしまう子もいるし、それはそれぞれだと思うんですよ。私自身、植田(紳爾)先生から、“根っこは宝塚やからな”とよく言われるのですが、その根っこに養分を与えてくれたのは、いろいろな劇団の演出家や、東京へ出て来てから出会ったたくさんの人たちなんです。だから彼女たちも、様々な物を吸収し、自分でチョイスして、自分の物を出して行ってほしいんですよ。いろいろな演出家と仕事をするうちに、どの人が自分に合うか、自分で選んで、これは面白いなあと思う人とは、どんどん仕事していったらいいと思うし、ありきたりのことですが、やる限りは挑戦していかなくちゃ絶対ダメだよというのはよくアドバイスしますね。宝塚でトップスターになっても、これで芸術はオーケーではなく、学ぶ所はまだまだこれからあるんだから、リセットして、もう一度勉強し直すようにって。彼女たちは小さい時から舞台に立っているから、根は舞台が好きなんです。だから、それぞれに自分の生き方を決めていきながら、いろいろな人たちと出会って、宝塚の根っこにとりどりの花を咲かせていけばいいのかなと思いますね」
――謝先生も、まず振付家になるために、たくさんの出会いがあったのでしょうね。
「私は、こんな風に振付家になろうとは思っていなかったんですよ。すべてが想定外でした。宝塚を退団して、結婚するまで1年間ぐらいダンス教室で教えてればいいと思っていたら、振付家の山田卓先生が、“NHKの『歌のグランドショー』の仕事があるから、上京して1年間やれば箔がつくで”と(笑)。そのひとことがすでに想定外で、振付家になるとも演出家になるとも、それどころかこんなに長く東京にいることになるとも思ってもみなかったんです。でも、もし私が人生を計算して生きていたら、もう取り返しがつかなかったんじゃないかなあ。基本的に強そうに見えて、本当に甘ちゃんですから」
――謝先生の現在は、テレビ番組の振付から始まったわけですね?
「最初は山田卓先生の振付助手でした。でも番組は週1回なので、並行して、やはり卓先生の紹介で、劇団四季の方々にダンスを教えていたんです。参宮橋にあった劇団四季の付属研究所でもずいぶん教えました。その後、二期会の人たちから、『マイ・フェア・レディ』をやるので、振付をやって欲しいと頼まれて、それを観た人が、東京キッドブラザーズの東由多加さんに私を紹介したんです。その時初めて、東京キッドの『彼が殺した驢馬』を観て、翌月には『冬のシンガポール』を振付していました」
――いきなり振付はできるものなのですか?
「元々振付を考えるのは嫌いではなかったんです。中学校の時、『マシュケナダ』という曲を振付して、みんなでダンスを踊って、文化祭で1位を取ったこともあるんですよ。さらに、『ネズミの嫁入り』をミュージカル化して、今や中山寺の偉いお坊さんになっている同期生に、“美術やり!”と言って、絵を描かせたり、その時から演出してますよね(笑)。しかも、主役のネズミのお父さんまで演じて(笑)。やっぱり嫌いじゃなかったんですね。演出家になったのは宿命のように思われる方もいるようですが、まったく自分では意識していませんでした。宝塚を辞める時も、本当は実業家になりたかったんですから(笑)」

――お話を伺っていると、突然方向が変わってもそれに対応されるのは、かなり柔軟性が高くないとできないように思います。
「やっぱりこれも客家の血じゃないかなと思いますね。柔軟性がなかったら、その土地にはなじまないわけですから。ここから振付家として、数えきれないほどたくさんの個性的な演出家と組ませていただきました。この時に、順応性や協調性も育まれたのだと思います。でも実のところ、30代から40代になるまでは想定外の連続で、毎年、"もう大阪帰るわ"って言っていました。こうして話すと、我ながら面白い人生だなあと思います(笑)。今後の夢は、淡路島にシアター・レストランを作ることなんです。これで実業家の夢も叶うかもしれません(笑)」
Text●原田順子 Photo●源賀津己 取材協力●パソナグループ
しゃ・たまえ 宝塚音楽学校首席卒業後、宝塚歌劇団に入団。退団後、NY留学を経て振付家として夢の遊眠社、こまつ座などに参加し、演劇的踊りが高く評価され、演劇界に衝撃を与える。その後も劇団四季、宝塚、東宝などのミュージカル、映画、TVで振付家として活躍し、1990年演出家に転向する。宝塚では演出作品も『激情』『凱旋門』など多数。受賞歴も多く、第43回芸術選奨文部大臣新人賞、第20回菊田一夫演劇賞を受賞した他、2008年には第43回紀伊國屋演劇賞個人賞、第16回読売演劇大賞最優秀スタッフ賞を受賞している。
TSミュージカルファンデーションHP
TSミュージカルファンデーション
オリジナルミュージカル
『客家 〜千古光芒の民〜』
11月9日(金)〜18日(日)
天王洲 銀河劇場(東京都)
※チケットは8月4日(土)一般発売
『天空の調べ〜文天祥物語より〜』
8月11日(土)〜12日(日)
淡路市立しづかホール(兵庫県)