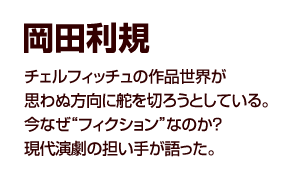──では話題を変えます(笑)。先ほどおっしゃっていた「今、置かれてる立場」は、まさに今日、お聞きしたいことのひとつです。岸田國士戯曲賞の審査員を今年から引き受けられましたが、やはり演劇界の将来を考えた時の責任のようなものを考えてですか?
「最初はできないと思ってたんですよ。実は打診をもらう前から考えていたんです、もし依頼されたら自分にできるかって。というのは、戯曲って何なのかよくわからないと思っていて。だけどそれがちょっと、自分なりにわかってきた。審査って「Aさんの戯曲の方がBさんの戯曲よりいいです、なぜなら……」という話をする場だと思うんですけど、その基準を自分なりに言える気がしてきたんです。
それが何かと言うと……、そうだな、たとえば役者でイメージしてください。見た目が役と合っていて、戯曲に書いてある感情をちゃんと理解できて、せりふが丁寧に言える人がいる。それがいい役者かと言うと、むしろつまらないじゃないですか。いい役者というのは、どこか挑発するというか、わずらわすというか、収まりきらない部分がやっぱりあると思うんですよ。稽古場なり役のイメージなりを、壊すとか乱すというやり方で、その作品に寄与することが出来る人が、僕はいい役者だと思うわけです。戯曲も同じで、そういう仕方で演劇に寄与する戯曲があって、そういう観点で選ぶことが僕はできるなと思った。あとはもっと単純な話で、選考委員の中で相対的にということですけど、若いポジションのうちにやっておきたかった。
それと、賞の意味もありますよね。賞というものを純粋に価値あるものとして考えると、やっぱり苦しい。だって「賞なんてくだらない」と言ってしまえばそれまでで、それはそれで真実ですから。だけど、じゃあなぜ僕が岸田戯曲賞に意味があると思うかと言えば、やっぱりあれは権威がある賞なんです。権威もまた、ある意味くだらないものなんだけど、それでも意味があると思うのは、その権威をもって公の世界に劇作家を引っ張り出す。僕は召集令状だと思っているんですが「世の中のために仕事をするように」という召集令状を渡す。それぐらい「命令」なんですよ、僕の岸田賞のイメージは。その選考を引き受けるのは、ある才能を褒め讃えるんじゃなく「そういう責任をあなたは担うか」という問いを突きつけるイメージ。で、それを誰に突きつけたいかという感覚で、僕は選ぶ」
──公の場と言う戦地に赴かされてるのは、岡田さん自身の実感ですか?
「うーん……赴かされてるとは思いませんでしたけど、僕の中では今の考えが整合性がつくんです。「賞はくだらない、でも賞には意味がある。権威もくだらない、でも権威ある戯曲賞の選考委員をやる。なぜかと言えば」という理屈の。
受賞した立場で言えば、僕はいかんせん、本気で無名だったから(笑)。「やったー!」みたいな気持ちでしたよ。その意味では、僕から言わせればほとんど誰もが「あなたは賞を獲らなくたって、もう充分やれてんじゃん」という気持が根底に常にあります。それが選考の時に反映されているかはわかりませんけど」
──初めての選考会はいかがでしたか? 今年の協議はかなり長時間で、受賞者3人という異例の結果になりましたが。
「選考会はおもしろかったですよ。もちろん、すっきり話がまとまったわけではないですけど、選考過程を(授賞式で)説明するスピーチを僕が担当するので、そのあたりを詳しく話そうと思っています。これは僕の個人的意見ですけど、選考委員が感じたことをもうちょっと公にした方がいい。「我々は今回、このような経緯でこういう結果を出しました」という経緯を、それをベースに議論がされる程度までオープンにして。それが責任かと考えています」
──演技論、芸術論の本を今年中に出版予定とのことですが。
「内容は、僕がこの時期に、こういうことを考えながら、この作品をつくったという記録というか。それが何になるのかはよくわらかないんだけど、でもまぁおもしろいかな、と。それを遡る形で書いていこうかと思っています。だからタイトルが『遡行』。新しい作品から書いてって、後ろにいくほど古くなっていく」
──とすると、『現在地』が一番最初に来て、まさに“岡田利規の現在地”になりますね。
「そうだ、そうですよ。『家電のように解り合えない』で終わらせるつもりだったけど、1章多く書かないといけないですね」
──ちょっと話は逸れますが、『現在地』と『目的地』(2005年)の関係は?
「『目的地』をつくったときに、いつか『現在地』というタイトルの作品をつくりたいとは思っていたんですが、それをすっかり忘れてて。今回なかなかタイトルが決まらなかったんですが、ある時、思い出したんですね、それで、あ、これだな、と」
──その『遡行』で、岡田さんが平田オリザさんの本を読んで演劇にのめり込んだような出合いを、若い世代にしてほしいという気持ちは?
「出合いの想定はしていませんが、その可能性がずっとゼロにならないのが本のいいところですよね。要するに演劇は劇場で出合うわけだけど、本はもし絶版になっても世の中から消えるわけじゃないから。そういう意味では、永遠に出合いの可能性があるし、それは僕が知らなくても全然構わない、みたいな。そういう広がりがいいですよね。だからそれが演劇を志す人じゃなくてもいいし、アート的なものに関心がない人でもいい」
──今、演劇論を書こうと思われたのは、最初におっしゃっていた「人類の英知である演劇」に、より多くの人に触れてもらうためでしょうか? 演劇の有効性をアナウンスする役割みたいなものを、背負う責任を感じているとか?
「それは全然思ってないです。いろんな意味で思っていない。例えば、演劇界を背負うってことは思ってないです。ただ立場が……、なんて言うのかな、引き受けようと思えばいろんなことを引き受けられる立場にいるということは自覚しています。全部が全部ってわけじゃないですけど、出来る限りは引き受けたいと思う。それで少しでも、社会に対して何かができるのであれば。ただ、さっきも言いましたけど、演劇のためだけに本を書くわけではありません。僕というひとりのつくり手が考えてきたことを言葉にしておくことで、それが何かの意味を持つなら、ある響きを持つのなら、単純にいいんじゃないかと思っている、ということですね」

──さて、最後に震災の話ですが。多くの劇作家がそのことについて語り、作品のモチーフにしています。そんな中でも特に岡田さんはヴィヴィッドに反応していらっしゃると感じます。リアクションすることが良い悪いではなく、岡田さんのようにストレートに言葉にしたり行動に移したりするのは、表現者として勇気があると思うのですが。
「えーっと、どういうふうに話せばいいだろう……。例えば僕は(放射能を避けるために)九州に家を移したんですけど、そういうところから見えてくるものですよね。僕はつくり手なので、震災なら震災とどう距離を取るかについて、スマートと言うか、デリケートにやること自体がなんとなく嫌だったんですね。だから素直に行こうと。もし動かなかったら動かなかったってことを素直に書くのが僕のやりたいことなんです。でも、たまたま動いちゃったので「動いた」とか「すごく怖いんですけど」と書く。
この作品とも関係するんですけど、震災を機に、何が正しいとか、そういうことが崩れてバラバラになったじゃないですか。今、「勇気がある」とおっしゃったけど、それは逆で、どんな意見を言うことも、必要な勇気の値は下がったと思うんですよ。だって、それが絶対じゃないことが明らかになったんだから。以前に比べると「自分がこれから言うことは正しいか?」といったことを気にしないで済む、それが僕の正直なところで、むしろ、勇気を要さず言ってるし、書いてます」
──ただ、一連の言動と作品──震災を避けての引っ越しについては小説にも書いていらっしゃいますね──で私が再確認したのは、チェルフィッチュは外側の方法論で語られがちだったけれども、テーマに選んできた雇用者問題やイラク戦争は、劇作家・岡田利規にとって本当に気になる問題だった、書かずにいられない問題だった、ということです。
「うん。でも変な話、今の社会と作品の実態が全てではないので、僕はあまり(テーマの時事性について)気にしてないんですよ。(作品として)しっかりしたものができれば、この後も残るわけで。震災から1年余りを経た日本の社会をコンテクストとせずとも、そんなことをまったく知らない国とか時代に上演される可能性もあるんですよね。震災直後に僕はチェーホフの『桜の園』を読んで、あまりに予言的で感動しました。でもチェーホフは、単にその時代のロシアの状況を元にあれを書いたのでしかないはずで、旧来の貴族社会が終わっていく、それに対する彼の応答、リアクションだった。優れた劇作家には先見性がある、とかそういう話だとはあまり思わない。ある作品が未来の状況と呼応する偶然が生じる。だから僕は今に対して、素朴にと言うかベタに応答する。それに「その先の続き」が生まれればそれでいい。それがいいなっていう意味で、今のこの日本社会のためだけに(演劇を)やっているわけじゃないという意識が、どこかにあります。そうすると、何を扱ってもさほど勇気みたいなものは必要ではない感覚が、僕には生まれるんですよ」
──この『現在地』も、すでに海外で上演が決まってるんですよね。
「何か所かは。でもそれらの上演は、震災を経た僕という日本の劇作家がつくった作品ということが、ありていに言えば“売り”になってしまいますね。よくも悪くも。震災というコンテクストからまったく切り離された状況で上演される可能性は、もしあるとしてもまだまだ先ですよね」
──チェルフィッチュは非常に精力的に海外公演を続いてらっしゃいますが、岡田さんにとって海外公演はどんな意味を持っていますか?
「いろんな意味があります。まず、まずは仕事としてすごく重要です。経済的な意味でとっても重要なんです。あとは、演劇が誰に向かってつくられるのか、どこに向かってつくられるのか(という意識の発生)。以前、「新潮」で飴屋法水さんと往復書簡をやった時に「神様に向かってやる」みたいなことを宣ったわけですけど、ああいうビジョンも、たぶん海外公演をしないと得られなかったと思います。『三月の5日間』の初演の時は、コンテンポラリーな東京の観客に対してやる以外のビジョンなんて持っていませんでしたから。関西で公演して「東京の芝居、気取っててあかんわ」みたいなノリでさえ、僕にはびっくりでしたから。同じ日本でもコンテクストが共有できない人がいる、それにさえ衝撃を受けていたのが8年前で。だから(海外で)言葉もわからない人達の前でやるのは、そして受け容れられたのは、すごく大きな経験でした。だからそれはその後の「どういう作品をつくるか」にもすごく影響してるし、自分達のパーフォーマンスが相手にする観客のイメージの持ち方が、完全に変わりました。たとえば去年やったバージョンの『三月の5日間』には、その成果が入っている気がします。テキストが変わったわけじゃないんですけど、パフォーマンス自体がすごく強くなっていて、その強さは、そういう経験(で得たもの)に他ならないですよね。だからとても重要です、海外でやることは」
──海外の評価と日本の評価のギャップに苛立ったりとか、そういうことは?
「そこに苛立ちはないです。ないんですけど、うーん、なんて言うのかな、それこそ原発の情報が海外から伝わってくるのと日本のメディアの発表で違うような、温度差というか、差を感じることがあって、そういうものが存在すること自体には苛立ちを感じます。でも僕たちの海外の活動が日本で紹介されることによって、それが何かの広がりを生む気はしていて、これは本当に格好をつけるんでもなんでもなく、だったらもっと紹介されたらいいのに、と思います」
──話は戻りますが、岡田さんが気付いた「演劇は人類の英知である」ことが、世の中の多くの人には気付かれないし、理解もされにくい現状がありますよね。その状況に対して岡田さんは、どう働きかけていかれますか?
「英知がそうなのにそう思われていないのは、例えば我々が星空を見ても、昔の人のように方角がわからないのと同じだと思うんですよ。で、それを「お前が勉強してないからわからないんだ、勉強して星を見たら方角がわかるんだ」と言われても、そりゃそうなのかもしれないけど、そんなこと言われてもなって、なりますよね。これと全く同じで。「演劇は有効なんですよ」に対して「なんかピンと来ません」と言う人には、やっぱり演劇が有効に働いている現場を目の当たりにしてもらうしかない。それをやりたくて、今日も結構厳しいリハーサルをしていたわけです。これまでグダグダなリハーサルをやっていたわけではありませんけど(笑)、今回は僕、役者に対してちょっと厳しいです。キツいことも言ってます。でも、それができれば“目の当たり”をつくれると思っていて。それをつくって見せればわかるって僕は信じてて。だからそれが僕の取っている唯一の行動です。でも本当にそれを、フィクションが有効なんだということをやりたくて、この作品をつくってるから。
観客の立場の人間が舞台上にいなくても、この作品は成立するはずなんです、本当は。でも、この「本当は」は、「本当は星を見るだけで方角がわかるはずだ」と同じで。それに対して「ちょっとヒントくださいよ、そのままじゃ無理っす」っていうのはあるじゃないですか。だったら、僕自身があの仕掛けによって助けられるから、じゃあやってみようかって。フィクションの力を信じるためのやっているって感じですね」
Text●徳永京子 Photo●源賀津己
おかだ・としき 1973年生まれ、神奈川県出身。演劇作家、小説家、チェルフィッチュ主宰。1997年、チェルフィッチュを設立。2004年に第13回ガーディアンガーデン演劇フェスティバルにて上演した『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。2007年にデビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(新潮社刊)を発表し、第2回大江健三郎賞を受賞。
チェルフィッチュHP