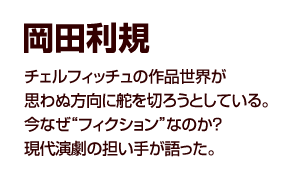その作品と言動が常に注目される作・演出家、岡田利規。国境もジャンルも当然のように超え、豊かなボキャブラリーをクールに駆使して進んでいく存在は、この10年近く"新しい演劇"の象徴だった。その岡田が今、「お話をつくるのが楽しい」と、演劇のスタンダードにスタートポジションを定め直した。とは言え一筋縄のスタンダードではなく、チェルフィッチュ流のひねりが存在する。作・演出家として、演劇人として、大きな変化を迎えているらしい岡田に、新しく目指すものについてじっくり聞いた。
──途中までの脚本を拝読して、また、稽古も見学させていただいて、『現在地』にはチェルフィッチュの、いわゆる代名詞なスタイルがないことに驚きました。反復される動き、言葉と体のズレ、語っている人物がいつの間にかすり替わっている独特のモノローグなどがまったく見当たらない。岡田さんがそれらに飽きてしまったのか、それとも一時保留なのか、あるいは別の理由なのか、まずそこから聞かせてください。
「もう2度とあれをやらないのかと言えば、特にはっきり決別をしたんじゃないと思います。あとから考えて「そんなつもりはなかったけど、考えてみたらあれから1回も会ってないな」っていう友達、いるじゃないですか。そういうことはあるかもしれませんけど(笑)」
──『現在地』をつくろうと考えた時に、それらが必要ではなかった?
「えーっとですね、今回やりたいのが「フィクションを上演する」ということなんです。フィクションが持っている力、働き、それを用いたい。
僕は今まで、いろんなことを疑う、ということをやってきたと思うんですよ。例えば「自然さとは何か」とか「役とは何か」とか、あとはまぁ、「演劇とは何か」とか。でも今やりたいこと、やるべきことは、そういうことではなくて、演劇という装置を有効に用いると、我々にどういう作用がもたらされるのかを考えたい。と言うのは、演劇って、人類の一種の英知だと思うんですね。個人的にはそれにアクセスしたいし、観客に対してはそれを用いて関係したい。そういう(以前とは異なる)欲求があり、それに向かってつくっているので、今までやっていた方法とは全く違うやり方になるんでしょうね」
──疑うことをやめたのは、疑わなくてよくなったんでしょうか、それとも……。
「疑う、疑わないどころの問題じゃなくなったって感じですかね。疑うよりも、演劇という装置の力が我々に必要なこと、私達に大きなものをもたらすという(可能性を実行に移す)ことのほうが先に来た、ということです」
──「演劇は人類の英知である、有効に用いれば大きなものをもたらす」という気付きは、劇作家、演出家として非常に大きなものだと思いますが、それを得たのは外的状況からですか?
「僕の中では震災がすごく大きいです。あとは経験と、自分が今置かれてる状況。状況というのは、震災後の日本の状況ではなく、演劇のつくり手としての僕が置かれてる立場みたいなものですね。そうしたもの全部からだと思います」
──震災は大きなキーワードなので、あとで詳しくお聞きするとして。先ほど「観客にアクセス」とおっしゃいましたが、それはすでに実行に移されていますよね。『わたしたちは無傷な別人である』(2010年)が最初だと記憶していますが、その時点ですでに高い完成度で実現されていたと思います。私はあの作品で、見えないはずのものを見たり、舞台上から催眠術をかけられたように強い波動を感じたりしました。『現在地』で改めて取り組もうとしている「アクセス」は、さらなる広さや深さにトライということでしょうか?
「うまく自分で比較できるかわからないんですけど『〜無傷〜』は、初めての試みのつもりでやって、結果的にものすごく満足の行くものができました。だからこそ、あの手法をそのまま別の作品にも、とは考えなかったんです。できないと思ったし、そういう興味も湧かなくて。で、あの作品は「舞台上で演技をすること自体が嘘だから、それはやらないけど、あるシーンなり人物なりが、つまり演劇が、観てる人の中で立ち上がるのは本当のはずだ」ということをやったわけです。舞台上で行われるのは嘘だから意味がない、価値がない、どうでもいい。ただひたすら、観客の心の中に演劇を立ち上げるためだけにやるっていう、すごいハードコアな作品だったんですね。
かたや今回は「舞台上で起きていることはみんな嘘です、人の名前すら役名で嘘です。でもそれをひたすらやります」。なぜやるかと言えば、そのことに意味があればやっていいんだと、今の僕は気が付いたから。さっきのリハーサルでも(会話している俳優を取り囲むように椅子を配して俳優を座らせ)観客的な存在を舞台上に置いていましたけど、それは、フィクションが機能している場をお客さんに見せたいんです。観客的な存在が舞台上にいて、それでも、あるお芝居が空虚なものではなく、有効に機能しているという情景が見せられれば、舞台の真ん中で行われていることが嘘だとか芝居っぽいということはすべて、僕としてはオッケーになっていく」
──『〜無傷〜』も『現在地』も、観客の想像力にアクセスするルートをつくっているけれども、そのルートを照らし出す方法がまったく違うということですね。さて、そのフィクションですが、これまでも演劇という表現を扱ってきて、今改めて前面にフィクションを打ち出しているのは、なぜでしょう?
「それは、僕にとってフィクションが新しいことだからです。演劇全体にとっては当然、新しくもなんともない。だけど僕は、僕はですよ、発見したんです。そんなの何千年も前から発見されてるよ、というのは知ってはいるけど、それでも自分で発見するというのはすごく重要で。そういう勝手な(笑)盛り上がりがあって「フィクションを上演したい」と」
──教えられた近道より、自分で歩いて体で覚えた道のほうが、達成感はあるし、その先に進む大きなモチベーションになるのはわかります。
「だからかなり盛り上がってますよ、「フィクション、おもしろいなぁ」って。これを人に見せてどうなのかまで含めて、すごく楽しみ。でも、危険な匂いはいっぱいします(笑)。だって下手したら「普通の演劇じゃん」で終わりますから」

──でも岡田さんはずっと、危険なほうの道を選んでいますよね(笑)。
「そうなんです、延長なんです、どんどん危険になっていく(笑)。でも普通は「危険」と言うと難解でわからない方向なんだけど、「ただの普通じゃん」と言われる危険の方がもっと恐いかもしれない、という覚悟はあります。だけどほら、なんせ発見しちゃいましたから(笑)。それを考えると、今までのチェルフィッチュとの方法論と関係あるとか無いとか、どうでもいいっていう感じなんですよ」
──そこまで多くのものを賭けるとすれば、岡田さんが定義する「フィクション」を、やはりお聞きしなければなりません。
「フィクションが現実とどういう関係を持っているのかがわかったんです。それは、やっぱり震災の影響が大きい。つくり手の僕にとって震災の一番の影響は何かというと、現実の社会が──今までだってそんなに揺るぎないものだとは思っていないつもりでしたけど──物凄く危うくて、決して確かなものではないということを強く実感したし、そういう感覚を持つ人が一気に増えた気がするんです。“あからさま度”があからさまに上がったというか。 その時にフィクションは、現実にただ対峙するとか、入れ子構造とか、そういったものよりもっと密な関係が結べると思ったんです。言ってしまえば緊張関係ですね。現実と緊張感のある関係が結べるものは何かというと、もはやフィクションしかない。そういうものに見えてきたんですよ、フィクションが。だから(それまで感じていた)現実とフィクションの違いがなくなってきたというか。つまり「フィクション=オルタナティブな現実」、あるいは「現実=今のところ支配的なフィクション」みたいな。そんな感覚が増してきて、フィクションを採り入れることが必要なんだと思ったんです。
これまで僕は現実をどう鋭く描くか──つまり、現実をすくい取って、切り取って、舞台上に乗せて、いかにそれがリアルか、深く社会に斬りこめるか、というような発想でつくっていたところがあると思う。だけどこの作品はまったく違って、ただひたすら、舞台上にいる人と人の間に何を置くと、テンションなり、バイブレーションなりが上がるかを考えてお話をつくっています。以前は馬鹿らしくて考えられませんでしたよ、お話だけで人と人を動かすなんて。それが今、僕の中で馬鹿らしくなくなってきた。ある登場人物が、どういうことを考えている人間かを考えることが、僕の中でマジでやれるようになった。つまりフィクションがつくれるようになったんですよね。うまくつくれるかどうかの自信はないけれど、でもそうやって僕はフィクションをつくれる。もっと正確に言うと「つくるぞ」と思える。それはかなり大きな変化です」
──『月刊新潮』の「震災であなたは何が変わりましたか」というアンケートで「想像力がほしいと思うようになった」と回答を寄せていらっしゃいましたが、今のお話と同じことだと捉えていいですね。
「まさにそういうことです。『新潮』で言ったのは、これまでの小説の書き方は「自分のブラウザの解像度がいかにイケてるか」みたいなことだと。「この解像度で見てると、ほら、現実はこう見えるんだよ」という。でもこれからはそうじゃなくて……という話です」
──とは言え、以前の作品と『現在地』が完全に分断されているようには、私には思えません。オープニングで、ある女性が別の女性に「今からする話を信じてくれる?」「自分は相手を選んでこの話をするんだけど」と切り出しますが、あれは観客に対しても言っていますよね?
「いや……、そういうつもりはありませんけど」
──じゃあ、こちらの深読みですね。私は勝手に、以前のチェルフィッチュの「これからお芝居やりまーす」というオープニングの変形、もっと言うと『〜無傷〜』で獲得した、観客の参加意識をサブリミナルに刺激して作品世界に取り込むノウハウを活かしたせりふだと解釈したのですが……。
「ああ、なるほど。そういうふうには全然思ってなかったんですけど、それもおもしろいですね」
Text●徳永京子 Photo●源賀津己
おかだ・としき 1973年生まれ、神奈川県出身。演劇作家、小説家、チェルフィッチュ主宰。1997年、チェルフィッチュを設立。2004年に第13回ガーディアンガーデン演劇フェスティバルにて上演した『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。2007年にデビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(新潮社刊)を発表し、第2回大江健三郎賞を受賞。
チェルフィッチュHP