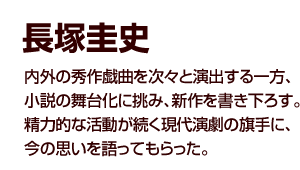――今年は1月の『十一ぴきのネコ』(作:井上ひさし)の演出に始まり、『ガラスの動物園』、『南部高速道路』、葛河思潮社での『浮標』(作:三好十郎)の再演、年末に予定されている『音のいない世界で』と、5作品を手掛けられる予定です。年間本数としては、長塚さんにとって最多になるんじゃないですか。
「そうかもしれないです。常に、次の作品の制作スタッフから追われていますよ(笑)」
――その多忙な中、昨年発表したばかりの『浮標』の再演を決めたのは?
「『浮標』は、1930年代という日本に大きな何かが起こりつつある時代の話です。昨年、その『浮標』を上演した直後に震災がありました。言葉は難しいですけど、おそらく震災前と震災後で、俳優の身体を通るセリフも変わるし、お客さんに伝わる言葉も変わってくるんじゃないかと。もちろん復興にはまだ時間がかかるでしょうし、慌てる必要はない。ただ、そういったことで何か考えるきっかけになるのであれば、いま再演することにも価値があるんじゃないかと思ったんです。なので一度観た人でも、できればまた観てもらいたいですね」
――『浮標』は長塚さんが立ち上げた演劇ユニット・葛河思潮社の第1回公演でもありました。葛河思潮社は、阿佐ヶ谷スパイダースの『アンチクロックワイズ・ワンダーランド』の作中人物であった作家・葛河梨池の思想を基点に活動すると宣言されています。葛河の思想について改めて聞かせてもらえますか。
「ものすごい観念的な話なんですよね。この僕たちに見えている物質的世界は、触ることはできるけど、本当は僕たちの思念でしかないんじゃないか。であれば、僕たちが存在しているとはどういうことなのか。物語の登場人物とどう違うのか。そういう物の見方は、観念的ですけど、生や死や生命といったことを考えることと、とても近いことだと思っているんです」
――『アンチクロックワイズ・ワンダーランド』は、様々な解釈のできる作品でしたけど、僕には劇作家・長塚圭史の「私演劇」のようにも感じられたんですよね。
「たしかに僕の中のある部分を引きずり出しましたからね」
――長塚さんにとっては、葛河梨池を生み出さざるをえない背景があったりしたわけですか。
「生み出すというよりは、現実的にそうなっていたんです。かつて僕は、やりたいことのできる環境なんだけど、それはイコール、常に新作を要求されることでもあるっていう時代があり、このままだといつか作品を生み出すことができなくなるなっていう危惧に陥ってしまい、海外へ脱出……みたいな(笑)、そんな流れがあったわけです。だから帰国してからは、単純に「僕の生み出した世界です」とか「面白いストーリーでしょ?」っていうものだけではなく、もっと観る側に作用していくような芝居を作りたいと思ったんですね。ただ、かつて悩んだ経験があったからこそ、「物語とは何か」っていう疑問とも徹底的に向き合うようになり、さらに葛河梨池が誕生したことで、彼ともいろいろ相談できるようにもなりました(笑)」
――長塚さんは劇作も演出もされますけど、帰国後は演出家としてのウェイトが高まっていて、それも作品ごとにケース・バイ・ケースで良さを引き出しているように見受けられます。
「いや、ホントそこが楽しいんですもん。どの作品も基本的に土台の作り方は一緒なんですよ。みんなで円になって、立ち稽古もそこでやって、役もグルグル変えて、徐々にお客さんのことを想定していく。「立ち位置どこ?」とか聞かれることもありますけど、「それは劇場に入らないとわからないし、いまは自分で考えてみようよ」って。まずは自分の頭で考えてみる。その作業がなかったらつまらないじゃないですか。だから僕はできるだけギリギリまで決めごとをしないんです。俳優にしてみたら、自分からやるのとやらされるのとでは違う。僕は、俳優というのは自ら思考する人たちだと思うので、13人の俳優がいれば、13人なりのアプローチがあってほしい。その上で、初めて僕も彼らに強く働きかけていくことができますから」
――年末に新国立劇場で作・演出を手掛ける『音のいない世界で』は子供も大人も楽しめる作品になる予定だとか。
「もともとは僕が首藤(康之)さんと飲み屋で話していて、「音が盗まれちゃったらどうする」「そりゃ追っかけるでしょう?」みたいな話をしていたら、どんどん転がっていって。これぜひ公演でやりましょうってことになったんです」
――発想とかディテールから作品が生まれているのが面白いですね。
「僕はテーマで演劇をやってるつもりがないんですよ。例えば、なぜ『南部高速道路』なのかっていうのも、渋滞というシチュエーションが想像をかきたてるとか、演劇の「見立て」という本質とリンクするものがあるとか、いろいろありますけど、つまるところは、「僕が面白いと思うから」なんです。じゃあ、何で面白いの? と聞かれても、理由はないんです。僕は南米文学を説明するときに、「どうして好きか」なんて話はしないですし、「どういう話なのか」をするだけなんです。ボルヘスの『砂の本』に、無限のページを持つ本にとりつかれる男が出てきます。その本はどのページも挿絵が違っていて、でもどこかのページに同じ挿絵が出てくるんじゃないかって探しているうちに生活も何もかもどうでもよくなってしまう。やがてその本を守るようになり、人がくると警戒するようになったりして、とうとう自分の異様さに気付いて図書館の奥の誰にも見つけられない場所に隠しに行くっていう。この話の何が面白いか? 「それはね、人間っていうのはやっぱり……」なんて言葉にした瞬間に消えてしまう感覚があるんです。その感覚こそが、僕が演劇で追い求めているものなんですよ」
――たしかに、その感覚は阿佐ヶ谷スパイダースの作品にも通底していますね。
「そう、初期の阿佐ヶ谷スパイダースではわからずにやっていたんです。ただ、いまはそういう志向があると自覚しているので、その上で、さらに自分の知らない領域にまで行ければと思っています。演劇って、原始的な想像力をいろいろ働かされるじゃないですか。ある種の感動もあり、歌もあり、踊りもある。そして、そこには、「答えはないし、何だかわからないんだけど……」っていう高揚もあると思うんです」
――それを聞くと、コクーン歌舞伎の脚本を手掛けられたときに、鶴屋南北の『桜姫』を、舞台を南米に置き換えて不条理劇として再構築されていたのもわかる気がします。
「あのとき書いてて面白かったのが、長い距離を歩いていく人たちが出てきますけど、演劇では、袖に入った瞬間に時空を超えられるんです。何年も何年も歩き続けて、数分後の世界にやってくるっていう。まさにコルタサルの世界に近い。ああいうことは理屈じゃなく、高揚しますね」

――最後の質問ですけど、長塚さんの目からいまの日本の演劇界はどんなふうに映っていますか。
「とにかく僕より若い演劇人が何をやっているか気になってしょうがないです(笑)。ほら、僕たちの世代はわりと上を見て、劇場のクラスとかを上げていくことに必死でしたけど、いまの若い人たちって自分たちのスペースでやれればいいっていう感覚が普通になってきているじゃないですか? そのこと自体は、演劇の多様性を考えればプラスだし、バランス感覚もいいなと思うんですけど、一方で、あるスケール以上の劇場を扱える演出家の欠乏も感じています。ま、僕もどんどんやっていくだけなんですけどね。今回、ワークショップに時間をかけたのも、そういう作り方を若い人だけの専売特許にしておくのが悔しいからというのもあるんです(笑)。べつに競うつもりではないんですけど、いろんな可能性を試したいですし、僕の作品にも、どんどん新しい世代の人たちに入ってきてもらおうと思っています」
Text●九龍ジョー Photo●源賀津己
ながつか・けいし 1975年生まれ、東京都出身。1996年、演劇プロデュースユニット「阿佐ヶ谷スパイダース」を旗揚げ、作・演出・出演の三役をこなす。2008年には文化庁新進芸術家海外留学制度にてロンドンに1年間留学。近年は積極的に外部作品の演出にも携わり、2011年に新プロジェクト「葛河思潮社」を立ち上げるなど活躍の場を広げている。2012年9月には葛河思潮社第二回公演『浮標』(作:三好十郎)の演出・出演が控えている。
阿佐ヶ谷スパイダース
葛河思潮社
葛河思潮社 第二回公演『浮標』
9月20日(木)〜30日(日) 世田谷パブリックシアター(東京)
※10/6(土)〜8(月)大阪公演、10/13(土)〜14(日)仙台公演、
10/20(土)新潟公演あり。
チケットは8月11日(土)一般発売開始予定。
新国立劇場演劇『音のいない世界で』
12月〜2013年1月 新国立劇場 小劇場(東京)