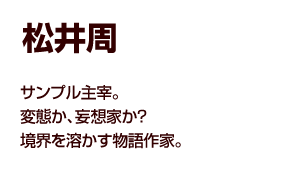サンプルの松井周は、『自慢の息子』(2010)で第55回岸田國士戯曲賞を受賞。以降、『ゲヘナにて』(2011)、『女王の器』(2012)では、さらにその「境界のない」世界を深化させてきた。松井が描くのは、ある人間の妄念が歪に膨らんで他人をも侵蝕し、呑み込み、呑み込まれてしまうような奇妙な物語世界だが、登場人物にはどこか愛嬌があり、なぜか憎めないのが不思議。今回はその代表作となった『自慢の息子』で、名古屋、三重、京都、北九州、東京、札幌の6都市をツアーする。
――『自慢の息子』は、引きこもりのような中年男が王として振る舞う国に、老いた母が訪ねていくというなんとも気味の悪い話ですが、松井さんの最近のテーマである「境界のなさ」がかなり前景に出てきた作品でもあったと思います。そのテーマはどんどん深まっていて、例えば先日上演された『女王の器』では、全てが夢のように曖昧な世界で、人間が人形みたいというか、有機物と無機物の「あいのこ」として描かれていたと感じました。
「あれは、どこから来てるんだろうなあ。発想としては「モノの視点から人間を見る」のが僕はどこか好きで。例えばずっと使ってるMacとかカメラを「相棒」って呼んだりする人、いるじゃないですか。ちょっと不具合があると「可愛い奴め」とか「お転婆だなあ」とか言ってみたり(笑)。つまりモノを愛着のある仲間として擬人化して物語を貼り付けておきながら、でもやっぱりモノでもある、っていう二重の見方をしたりすると思うんです。そうすると、境界がどんどん壊れて溶け合う感じがあって、死んだ人も夢の中で蘇ったり、あの人が今ここに居たらどう言うだろうと考えてみたり……。物語というものの根本に、何かそういう現実と虚構、生と死、男と女といった境界を溶かしていく力があると思うんですよね」
――普通は名づけたり、境界引いたり、カテゴリー分けしたりすることで物事を認識しますよね。そこから一種の倫理観も形成されるはずで、だからそんなに境界溶かして大丈夫なの?とも思うんですけど、なぜか『女王の器』では不思議な説得力をもって舞台が成立しているように感じました。
「『女王の器』で大変だったのは、本当にいろんな世界を混ぜすぎちゃって土台がないこと。もうね、本当に波に溺れてる感じになっちゃって(笑)。全部が無意味になっちゃったものをそのまま見せても何も面白くないし。でも、無意味の中にもう1回意味をつかもうとするところの、人間の藁をも掴む感じっていうのかな、その姿を描きたいなと思ってつくりましたね。例えば酔っ払ってる時に世界がぐるぐる回るでしょ。その時に僕がよくやるのが、とにかく目をカッと見開いて、身近にあるモノの場所を確かめて見るんです。ここがズレなければ、後は回ってても大丈夫!、みたいな感じになる時ないですか?」
――あんまりないです。
「あれ?(笑) 僕あるんですよ。だって目つむったら、グルグルの中に入っていきません? あれ辛いですよ! ヤバイぐわんぐわん回ってるって時に、呼吸を整えながら1点を見つめて、あ、ここの1点と繋がってる、僕は!、っていう物語を自分に課して、後は回ってても大丈夫だというブイ(浮標)を見つけるんです」
――なるほど(笑)。そういえば『あの人の世界』(2009)もかなり訳の分からない抽象的な世界でしたけど、しかし観客の視点を集中させる具体性のあるポイントが要所要所にありましたよね。例えばボールを宙に投げてキャッチしてる人がいるから、つい観客としては集中して見てしまうとか。
「それはね、すごく意識してます。サンプルの作品は、ある部分はリアリズムで成立してるけど、全体を引きで見ちゃうとどう考えても整合性が取れないな、ということが同居してるので、そこにさらに観客の五感に訴える要素を何か存在させたいと思ってるんです。例えばあのボールも、重力に跳ね返そうとして投げてるんだけど、それをキャッチ出来るか出来ないか、っていうその触覚や視覚を刺激したいというか」
――視線の集中と拡散が面白いといいますか、例えば『ゲヘナにて』では音源と光源がメチャクチャたくさん配置されてて、視点を絞り込めないというか、パッ、パッ、と明滅する感じで、観る人によって全然異なる世界が広がる感じがありました。
「『ゲヘナにて』ではまた別の要素として、積極的ではないにしても、お客さんに参加してる感覚を持って欲しいという狙いがありました。本当はですね、入口の通路に、大量の風船とかダンボールとかゴミ袋を置いておいて、それをどかさないと客席にたどり着けないスタイルを取りたかったんです(笑)。そのどかした痕跡が会場に残ってて、開演するとそのダンボールとかを使って俳優が演技し始めると。するとその1回でしかありえない演技の形や俳優のポジションが出来上がるはずなんですよね。しかもさらに音響が客席の後ろに仕込んであったりとか、照明が客席と舞台を分けないようになってたりとか。結局これは挑戦的というか冒険的すぎて実現出来なかったんですけど(笑)」
――もう全部溶かしてしまうという(笑)。でも音響と照明のアイデアは活きてましたね!
「ええ。俳優も、どの場所でシーンを始めてもよいというルールにはしてました。例えば上手で演じるとか、下手の上の方で演じるとか、ほとんど決めないで稽古して、しかもなるべく稽古ごとに場所を変えてやってくださいと。で、実際本番中も日によって違う場所で演じたんですけど、毎回変えるとタイミングとかもズレてしまう。きっかけも一応あるんですけど、結構ライブで、その日の感覚で。だから上手くいったり失敗したりはありました。基本的には、照明も音響も、俳優の立ち位置を考慮した作りではなかったですね。最初から全体を包み込むような、どこで俳優が何しても成立するように」
――どうしてそんなリスクの大きいことを?
「やっぱりそれも境界を溶かしていきたいんですかね……。でも、自分でも変だと思いますけど、溶かしたいという欲望と、逆に自分のフィルターを通した物語を見せつけたいって欲望もどこかあって。観客を体験させるだけだったら美術のインスタレーション的なものにすればいいんですけど、やっぱりオーソドックスな作劇の仕方も捨てられないんです。そこにいつも引き裂かれてますね。インスタレーション的になっていくことに対する憧れはありながら、なんで物語を捨てれられないのかな、って」
――松井さんはやっぱり物語の人だという印象が強くあります。描く世界や方法はかなりラディカルだけど、「物語を書いて上演する」こと自体は手放さないといいますか。
「きっとそれは台本も、これはよく僕が言ってる話で、どんどん〈確率が低い方〉に転がるように書いていくんですけど、その作業が結局自分を追い詰めてくことにもなるので、追い詰められて、うわあ全部無意味ってなった時に、もう1回意味をつくる作業に入るというか。そういう過程が欲しいんですかね」
――旗揚げ公演となった『通過』の初演(2004)を偶然にも拝見してまして、うわ、と思って面白かったんですけど、同時にかなり閉塞的で破滅的な世界だな、とも感じたんですね。あの頃って、物語ることの困難が演劇にかぎらず漂っていたと思うんですけど、だからこそ作家はみんなそれぞれ格闘してて、そうした中にあって松井さんも作品を重ねてこられた。で、ついに岸田賞を獲ることになった『自慢の息子』を観た時に、「ああ、まだまだ語る物語があるんだなあ!」と感動したんです。もう何もないかと思ってたけど、地球のマントルくらいまで掘り進めば全然何かあるな、という手応えといいますか。
編集部:松井さんは以前、東京宝塚劇場でもぎりの仕事をしていたんですよね。松井さんが宝塚とは意外でした。やっぱり物語が好きだからでしょうか?
「あ、そうです、そうです! 宝塚とか。実はベタな物語が好きというのもありますね(笑)。ほんとあの『通過』の初演の頃はチェルフィッチュとかいろんな劇団が出てきて、このままでいいのか、ってことを思っていた気がします。ベタな物語を呑気には出来ないなと思ってたし、ポツドールのように徹底的にリアルを突き詰めたり、あるいはチェルフィッチュのように少し抽象度を上げてくこともあり、その間に挟まれて、物語への抵抗はありながらも、模索しようと思いました。で、そのまま結局今も模索し続けてるんですけど、基本的にベタな物語は好きなんですよ」
――物語が好きになったきっかけは?
「僕ね、『ガラスの動物園』が本当にかなり好きで、高校の時に、姉ちゃんが大学の英語劇でやってたんですけど、そのあと台本を読んで。今思えば、トム、母アマンダ、姉ローラ、それからジム、それぞれの物語がね、全然噛み合ってないんですよ。あの噛み合わなさぶりが凄く哀しいというか」
――でも、とあるインタビュー(岩城京子『東京演劇現在形』に収録)によると、噛み合わなさを描くといっても、芥川の『藪の中』のようなことをやりたいわけではないんですよね?
「そうなんです、ぶつかり合いを描きたいわけではないんですよ」
――それは不思議ですね。物語を志向するとなると、普通どうしても構図とかプロットに意識が向きがちだと思うんですけど、松井さんは、バラバラにいる人たちを舞台という場所でただ成立させることを考えてるというか。
「他人の物語に自分も乗っちゃう、みたいなのが好きなんです。自分の物語がいつのまにか他人の物語によって改変されたり、自分が、他人の物語の登場人物の1人になっちゃう。対立するのじゃなくて、そういう包まれ方が滑稽というか面白いなあと。いわゆる集団における洗脳もそうかもしれませんけど、物語に飲み込まれていくことの快感や、流されてしまうことの弱さはある。そこを描きたいんです。だから構造的にはグニャグニャになって、一体誰の物語なんだこれは?みたいになっていきますので……」
――怖いですね。侵食し合ったり、入れ子構造になったり。主体性がなくなっていくという。
「そう! その主体性があんまりないっていう感覚が自分の中で凄く強くて。全部ほんと〈器〉でしかないというか。誰かが提示した物語になんとなく乗って漂っている感じがどうしても捨てられない」
――『女王の器』はスフィンクスの目線で書き始めた、と仰ってましたけど、人間の主体性からでなく、そういう外部の視点や流れを導入して物語を描こうという意図はありますか?
「それはさっきも言ったように、モノの視点で見たいという。物語のネガっていうのかな。人間は何かに対して勝手に物語を貼り付けるけど、モノからすれば、批判的にちょっと冷めた視点で見ることができるんです。例えばお地蔵様側から見たら、あれ? 俺、ただ流れ着いてきた石なのに、なんでみんな手合わせてるんだろう、とか(笑)。でもちゃんとご飯を持ってきてくれる人もいたり、なぜか挨拶する人もいたり、あるいは壊す人もいたり、唾吐く人とか」
――あ、ネガというのはつまり視点を反転させて突き放すという?
「そうです。人の行動が、あ、こういうこともありうるかも、って見えてくる気がするんです」
――それってつまり、ある人の内面的な動機よりも、モノを通して顕在化してくるやりとりに興味があるってことですよね。
「内面的な動機というのが僕にはよく理解出来ないんです。モノに誘われてるというか。そこに後付けで内面をつくることはある。もちろん内面も存在するんですけど、そっちはあんまり考えないでつくろうと。それよりもモノの形だったり、匂いだったり、言葉じゃない誘惑というか。まあそれも一種の言葉だとは思うんですけどね」
――モノといえば、松井さんはずっとゴミに対する謎の執着があって(笑)、よく舞台にゴミを散らかしたりしますよね。あれは何なんでしょうか。『家族の肖像』(2008)とかも結構。
「ああー、なんなんでしょうね? 『家族の肖像』はかなりゴミ散らしましたね(笑)。や、僕もそれは知りたいというか……。でも〈遊びをつくる〉って感覚はどこかあって、どうとでも人がいじれたり、邪魔に扱ったり、寝転んだりできるような。逆にきちんと整った空間だとあんまりモノに呼ばれないというか誘われないんですよね。例えばこのキレイな机をベッドだと思い込むには、やっぱりひとつ何かを乗り越えなければいけない感じはあるんですけど、でもゴミがあると、その境界も崩れてく感じがある。境界を崩す潤滑油みたいなものとして、ゴミがあるんじゃないかな」
――ちなみに松井さんの部屋ってやっぱり……
「汚いです!(笑)ほんとね、今大変なことになってます……。でも佐藤可士和さんの仕事場とか写真で見た時に、何これ!とか思った。パソコン以外何も置いてなくて、なんか武士みたいな感じっていうんですかねえ。憧れますけど。物語の作り方っていうのかな。環境づくりもひとつの物語だと思うから、そのきちっと整頓された空間もまたひとつの面白みだと思います。憧れるけど」
――松井さんの場合、もっとゴチャゴチャしたキッチュな感じ?
「そうですねー。そこで俳優がどうすんのかなってことを見てみたいという欲求はあります」
――そういう意味では、ゴミの存在は、俳優にとっては演じる上でのアイテムにもなるわけですよね。
「人によっては負荷になるかもしれないですね。整頓されたテーブルと椅子だけにしてくれた方がやりやすい人もいるでしょう。ゴチャゴチャと変な邪魔なものを置くので、ちゃんとセリフが言えないとか、いろんなことになってくと思うんですけど、まあ、その姿を見たいっていうね。ウフフ……」
――松井さんは「俳優がそこに立つ」ための根拠を常に意識してる気がしますが、それはご自身が俳優でもあることとも関係ありますか。
「ありますね。どうとでも出来ると思っちゃうんですよね。俳優に必要なものは、そこにあるものを使いながら着せ替えてくコスプレ感覚だと思うから。触感を使ったり、聞こえてるものをちょっと変換しながら……。例えばここは喫茶店ですけど、ここをお城のバルコニーに変換していく能力を俳優は持っているべきだし、そうできると思っちゃうんです。たとえ凄く貧しい環境であっても。だからその負荷が俳優にかかってるほうが面白い」
――それってある意味、俳優自身の持てるものをそこに出して欲しい、という要請でもありますよね。
「どうこの喫茶店を城に変えていくかって時に、たぶん俳優それぞれの出し方があるから。本気でそれを信じてく時の俳優の真剣さと足掻きは、俳優力というか、それが技術なんじゃないかと」
――となると、松井さんが所属してこられた青年団の平田オリザさんのメソッドとの違いはどうですか。基本的には青年団はあんまり余計なことをさせてないように見えるし、舞台空間も、オシャレなテーブルとか、清潔な美術館とか研究室みたいなキレイな場所が舞台になることが多い。そこらあたり、青年団との違いは意識されてますか? 言うなれば「オリザ超え」みたいな。
「うーん、でもね、やっぱり環境からつくる感じはオリザさんにもあって、例えばテーブルの周りに集まって人と話す距離とか、あるいはロッカーとの付き合い方とか、そういった環境を利用することでコスプレにしていく感じは、青年団とあんまり変わってないんです。でも僕の場合は、過剰に貧しい環境なのに違う妄想を貼り付けていく、ってところはあるかもしれない。確かに、環境を、もっと妄想で塗り替えてく感じはかなりありますね。そこは僕がやりたいことと、オリザさんが進めたいことはもしかしたら違うかもしれないんですけど。僕自身がやってることはあんまり変わってない感じはします」
――もうひとつ、いわゆる現代口語演劇からの距離はどうでしょう? 特に『女王の器』では、明らかにわざと現代口語演劇のリアリズムを捨てた過剰な演技が挿入されていました。さらには詩的な、文学的な言葉が戯曲として書かれて、それを俳優に読ませていく側面もあったと感じましたけど。
「ええ。ひとつは、やっぱり口語演劇がすごくデフォルトというか前提になってしまって、そこでの俳優の上手さはもう行くとこまで行ってる。みんな上手いんですよ。もうかなりこなせる。そうすると、こっちとしては負荷を与えたいっていうか、むくむくと意地悪な心が芽生えてきて、じゃあもっと全然違う言葉を喋ってみてほしいと思う。それから、口語的な連なりで人間を描くより、モノと人間が区別がつかない感じで書きたいから、もしかしたらこれはそもそも人間が喋ってる言葉じゃないかもしれない、ってものを取り入れていきたいんです」
――それって例えば、サラ・ケイン『パイドラの愛』、マリウス・フォン・マイエンブルグ『火の顔』、マティアス・チョッケ『文学盲者たち』をやり、さらに「producelab89 官能教育」でもマルキ・ド・サドを扱われてましたけど、そういう海外の戯曲や文学を演出した影響はあります?
「ああー、それはありますね、たぶん。どうしても口語演劇だと、演劇が演劇であることを気付かせないように進めてしまう部分がある。でも海外の戯曲を読むと、これは明らかに演劇です!、というところを出してきてて。そう思うと、まだまだ演劇ってレンジが広いというか。口語演劇というのも、袋小路というと言い過ぎですけど、ひとつの手段でしかないなって捉えられてきてて。だから何かしらの異物感を挿入して、常にどこかに穴を開けて別の方向にも行きたい。そうしないと自分も面白くないんで」
――そういえば『ガラスの動物園』って、作者のテネシー・ウイリアムズの前置きがやたら長いとか(笑)。
「や、ほんっと長いですよねー。いや凄いですよ。ト書きでいろいろきちんと書いてあって。テネシー・ウィリアムズってリアリズムの印象がありますけど、ちゃんと演劇的に異物感を残そうとしている。それは参考になったなあ」
――松井さんはかなりマンガがお好きらしいですね。
「好きです。いやもう、確実にあるのは楳図かずおさんですけど。恐怖だったんですよね。楳図さんの絵というか、あの佇まいというかですねえ。特に漫画を作品に取り入れようとかは全然思ってないんですけど、楳図さんの描く怪物とか、あとほんとに『漂流教室』って凄い話で、未来に学校が飛んでっちゃって、最初は大人もいるんですけど、大人の方が環境に適応できなくてどんどん自滅していく。子供も環境に適応しようとして頑張るんですけど、でも対立が起きて、ペストになった人たちを隔離して燃やそうとしたりとかするんですけどね。なんかもう、人間ってここまでひっくり返るんだっていうことの何かが植え付けられた。まあ本当に面白くてずっと読んでるんですけど」
――漫画的なぶっ飛んだ想像力って面白いですね。絵の運びとか、コマ割とか。ページをめくった時にぶち抜きで1ページ使うだけで、急に世界自体の広さが一挙に広がる感じ。
「あると思いますね。あとやっぱり楳図さんの漫画は黒が濃いんです。すごく黒いんですよ全体が。『まことちゃん』ですら暗い部屋なんですよね……。そのインクの多さに誘われた感じはあります。だからいつも怖いんです」
――サンプルの舞台も、地面は白かったりするのに全体の色調が暗かったり。
「暗いですね。やっぱりね、演劇って影が上手く使えるから。暗闇の、見えるか見えないかのところでモソモソ動いてるだけで、面白いというのはあるんです。観客の見ようとする積極的な何かを勝手に動かすものがある」
――なるほど。そして結構、イリュージョンはありますよね。やっぱり宝塚から繋がってる?
「や、宝塚は逆に凄く、光!って感じですけどね(笑)」

Text●藤原ちから Photo●源賀津己
まつい・しゅう 1972年生まれ、東京都出身。1996年に青年団に俳優として入団。2004年、青年団若手自主企画『通過 』で第9回日本劇作家協会新人戯曲賞入賞。2007年『カロリーの消費』で劇団サンプルを旗揚げ。2010年、『自慢の息子』で第55回岸田國士戯曲賞を受賞。小説やCM出演でも活躍。価値の反転した、虚無的だがどこか愛嬌のある妄想世界を描く。
サンプルHP
サンプル
『自慢の息子』
4月4日(水)〜5日(木) 七ツ寺共同スタジオ(愛知)
4月7日(土)〜8日(日) 三重県文化会館 小ホール(三重)
4月10日(火)〜11日(水) アトリエ劇研(京都)
4月14日(土)〜15(日) 北九州芸術劇場 小劇場(福岡)
4月20日(金)〜5月6日(日) こまばアゴラ劇場(東京)
5月13日(日) 生活支援型文化施設 コンカリーニョ(北海道)