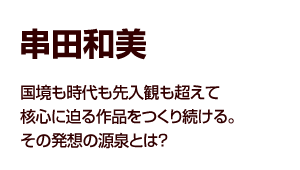『ファウスト』は、ずっと残っていた宿題
――串田さんの舞台は、具体的な空間づくりの工夫も為されていますが、舞台と客席の心理的な距離感が短い、あるいは互いの呼吸を交流させるという意識が前提にあるように思います。言い換えると串田さんは、観客の空気を非常に敏感に感じ取ってきた演出家だと思うのですが、60年代から2012年までの変遷をどう感じていらっしゃいますか?
「それを聞く? うーん……正直、あまりいい変化は感じていません。自分の中で分裂するような気もするけど、音としての言葉、言葉を発する状況そのものが演劇であって、書かれた言葉の奥の意味を探ることではないと思いながらも、意味を飛ばして観て“楽しい”とか“わからない”で終わってしまうことはどうかとも思うね。“楽しい”にしても"わからない"にしても、そう言うためには、観る側もよっぽど感性を研ぎ澄まさないといけない。
それはたぶん、演劇をつくる人たちの責任だけじゃなくて、いろんな媒体の体制にも深く関わっていく問題だから、非常に難しいですけど。だって、演技とは違うところでキャーキャー言われている人たちが舞台に出て、そういう人たちがたくさんの媒体に出て“それって一体どうなんだ?”とは思っても、“もしかしたら出雲阿国もそうだったのかもしれないしな”と思うと、むやみに否定できないものね(笑)。
もうひとつ最近考えるのは“影響って何かな”ということ。60年代や70年代は、なんだかんだ言っても、観客2〜3千人の世界でやってて、動員が5千人行ったら“すげー!”という時代だった。でもその2千人3千人のお客さんに与えた影響――その人が感動したということだけじゃなくて"こんなの、わかんねえぞ"と怒って帰ったことも含めて──、その人たちが別の時間に別の場所で何かを起こして、間接的ではあっても社会まで影響した時代と今は、ずいぶん違うんじゃないかということでね。今は、2万人観た、3万人来たと言っても、感動や興奮がその日のうちに終わってしまっているんじゃないだろうか。様々なメディアで採り上げられて、昔よりも社会を賑わしている部分はあるだろうし、公演数自体も増えているんだろうけど、その反面、失ったものもたくさんある、という思いも、正直あります」
――でも、串田さんが始められたコクーン歌舞伎は、平成中村座につながったり、演じ手も観客も若い世代へとバトンタッチされたりと、大きな形として残っているのではないですか?
「確かに自分としても、積み上げてきた部分に関しては手応えはあるんですけど、先のことを考えると不安もありますよ、当事者としては。もし僕が病気でもして5年やらなかったら、“そういえばあったよね”で終わるんだろうな、とも思うし。歌舞伎の人は、それが良さでもあり、だからこそ伝統として続いているんだろうけど、どんなに新しいことをしても、またすぐ戻ってく力が強い。だから僕の立ち位置は、これは最初からそうですけど、歌舞伎を改革しようとは思っていなくて“歌舞伎は演劇だよ”ということを言い続けている。お囃子を使わないとか、宮藤官九郎君に脚本を書いてもらうとか、いろんなことをしていますけど、それも奇をてらうつもりじゃなくて“ほら、こういうことをしてもいいでしょ? だって歌舞伎は演劇だから”というスタンスなんです」
――歌舞伎も演劇のひとつだとすると、『K.ファウスト』も、コクーン歌舞伎と同じ頭で考えてらっしゃるということですね?
「そうですね。歌舞伎を観ていて、浄瑠璃や竹本って本当は物語を解説しているはずなのに、あんな唸っちゃわからない、という問題があるでしょ?(笑)。そこから考えて、ひとり語りとお芝居を行き来するような演技ができないかな、と。自分が自分に“この人はね”としゃべっているうちに、だんだんその人の話に入り込んじゃったり、そこからまたポンと出てきたりするような」
――そもそもなぜ『ファウスト』をやろうと?
「僕が10代の頃は、新劇が最先端だったんです。“モスクワ芸術座が初来日するぞ!”とか“コメディ・フランセーズの『スカパン』が来た!”とかね。よく意味もわからないままに興奮していたものがいっぱいあるんですよ。そういうものをそのままやるのは、もちろんダサいしダメなんだけど、でもどこかで、古いからといって捨てるのも違うな、という意識もずーっとあったんです。自分があれだけ感動したのは何だったのか、それを考えることが、人生の宿題みたいな感じで残っていた。
それで60歳を過ぎた頃に緒形拳さんと“こういうやり方はあるのかな”って『ゴドーを待ちながら』をやったり、『スカパン』はこうしたら自分の新しいスカパン像になるんじゃないとか、実践してきたんですよ。その中で最後まで残っていたのが『ファウスト』。自分でもどうして『ファウスト』にこだわるのか不思議だったんだけど、ワークショップでテキストと向き合ってみると、ゲーテの時代の神に対する新しい発想とかがあって、ああ、(作者は)戦っていたんだなと」
──戦いの相手は、その当時の古い宗教観ですか?
「そこの設定がすごく難しい。確実にキリスト教について書かれているんだけど、僕らがそれを扱うと、どうしても途中で思考が止まっちゃう。だから、キリスト教がどうとかじゃなくて、なぜ人間が神というものを想定しなきゃ生きられないんだろう、という問題に置き換えたの。宗教というよりは哲学的な問いだね。だから、戦うのは“わからないもの”と言ってもいい。特に現代の僕らは、何でもかんでもわかったつもりになって、なんでも制覇したつもりでいたけど、そうじゃないということは地震でわかったし」
――『ファウスト』は、悪魔と契約して万能の力を手に入れ、地獄に落ちる男の話ですから、宗教を外に置いてそれをやるというのは、斬新というか新鮮ですね。
「有名な『ファウスト』はゲーテ作だけど、もともと彼はマーロウが書いた『フォースト博士の悲劇』を観ているし、人形劇とかで演じられた古い『ファウスト』も子供の頃に観ているらしい。もっと遡れば、その場に集まった人を楽しませたくて誰かが話をこしらえて、聞き手があくびをしたところは端折って、おもしろがられたところは膨らませて、近所のおかしなヤツのエピソードも入れて……そうやってできたはずなんです。そう考えると、決して難しいものじゃない。ワークショップを何度か重ねて、そういう実感が伴ってきました。
演劇ってね、やってないとわからないことがたくさんあるんです。自分が舞台上で死んでいて“今、くしゃみしたら大変だ”なんて思っている時に、ぽーっと明かりが当たって、殺した人が自分を見下ろして何かしゃべっていて、観客が観ている。と、"もしかしたら、死ぬって本当にこういうことかもしれないなぁ"と感じたり。舞台のちょっと高いところにいて、客席が見えて、舞台で共演者が演じているのも見えて、引っ込んで着替えてる人も見えて、そんな時、誰もが一度は世界をこんなふうに見たら、世の中に対する捉え方が全然違うだろうと思う。“これをお客さんに見せたい”ってすごく思うんです。そのままは無理なんだけど、演劇にして見せたいって思う。演劇がつくる世界を演劇にして」
――それは、構造ではなく“真理のメタ演劇”ですね。
「そうだね。だいぶ前に、NYだったと思うけど、いろんなショーを観ている中で腹話術があったんです。すごく上手いんですよ。ストローでジュースを飲んでいながら、手に持っている人形が“俺のだから残しとけよ”って言う。いろんなテクニックをやって客席を湧かせていた。その最後に、彼が自分の靴下を脱いで、手にはめて、目のシールを貼ってアヒルみたいなのをその場でつくって、それと会話し出したの。そのうちケンカになって“じゃあ、どっちが正しいかお客さんに聞いてみよう”と言ったら、靴下人形のほうが正しいってことになって、使い手はだんだん怒って、そのうちに“こいつは俺がつくったんだよ? これ、靴下だよ?”と言い出して、最終的に手から外すと床に投げつけて靴で踏んで、鞄の中に入れちゃうわけ。でも靴下人形は鞄の中で喋ってる。それを観た時、こういう舞台がつくりたいと思った。テクニックもすごいんだけど、テクニックを超えたものがあるでしょう? 観ている人は靴下にシンパシーを感じて、そっちが可愛く思え、正しいと思う。そして、鞄の中で靴下が喚いているのを聞いて、感情が揺さぶられている。その不思議さってなんだろう。この構造ってその人すごいよね? 今でもそれが、僕の理想の芝居だね」

Text●徳永京子 Photo●源賀津己
くしだ・かずよし 1942年生まれ、東京都出身。俳優、演出家、舞台美術家。まつもと市民芸術館芸術監督。俳優座付属養成所、文学座を経て、1966年、斎藤憐、吉田日出子らとともに劇団自由劇場を結成(後にオンシアター自由劇場と改名、1996年に解散)。1985年から1996年まで東京・渋谷のBunkamuraシアターコクーン初代芸術監督を務める。2003年、まつもと市民芸術館芸術監督に就任。主な演出・出演作品にオンシアター自由劇場『上海バンスキング』(第14回紀伊國屋演劇賞団体賞受賞)、『クスコ』『もっと泣いてよフラッパー』など。コクーン歌舞伎、平成中村座の演出家としても知られる。
まつもと市民芸術館HP
『K.ファウスト』
10月6日(土)〜14日(日)
世田谷パブリックシアター(東京)
10月19日(金)〜21日(日)
まつもと市民芸術館 特設会場(長野)
『K.ファウスト』記者会見(9/27) の映像
『K.ファウスト』公開稽古(9/27)の映像