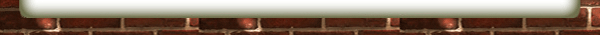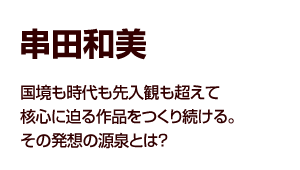近年は、数々のドラマや映画の父親役で、視聴者を唸らせたりゾクゾクさせたりしている串田和美。「こんな俳優がどこにいたの?」とネットで検索をかけた人も少なくないようだが、繊細さに支えられた奥行きある演技は、引き出しのほんの一部。ホームグラウンドの舞台では、60年代からずっと、国境も時代も先入観も超えて、核心に迫る作品をつくり続けているのだ。新作『K.ファウスト』の東京公演を前に、その核に近づくべく話を聞いた。
小3で不条理劇、中1でメタ演劇の洗礼
──串田さんが演出家として手がける作品は、コクーン歌舞伎や平成中村座も有名ですが、俳優たちが楽器を演奏して、音楽と物語が分かち難く結び付いてたオンシアター自由劇場時代のオリジナル作品、さらにモリエールやブレヒトなどの翻訳劇と、3つの系統に分けられると思います。一見バラバラに思えて、祝祭的な空気、サーカスを思わせる空間の使い方、グリム童話のような無邪気さとシニカルさの両立などが、共通して感じられます。それらは他の日本の演出家にはなかなか見られない傾向で、どういう経緯で串田さんがそれを身に付けていったのか、まずそこからお聞きしたいのですが。
「それはふたつあって、ひとつは小さい頃から出会ってきたもの、出会ってきた人たちの中で、僕が好きだったものが今につながっているという、本当にシンプルな理由ですね。
もうひとつは、僕が演劇を始めたのが60年中頃で、佐藤信さんや斉藤憐さん、吉田日出子さんと自由劇場を立ち上げたのね。みんなで来る日も来る日も、これからの演劇についてワイワイ話をして。で、気が付いたら向こうに唐(十郎)さんがいる、あっちには寺山(修司)さんがいる、彼らもいろいろやっているらしい、という状況になっていたんだよ。今みたいにネットなんかないから、そんなことをしているのは自分たちだけだろうと思っていたら、同時多発的にいくつも劇団が立ち上がっていて、それぞれのやり方で新しいことを始めていたんだね。あとから考えると大きな運動みたいに見えるけど、本当に個別の活動だったの。つまり、自分たちは何がしたいのか、そのためにはどうすればいいかを、みんなが考える時代だったんだね」
──最初は文学座に入団され、間もなく佐藤さんたちと退団された頃ですね。
「新劇の基本的な考え方は、とにかく戯曲を一所懸命、解釈するなり学ぶなりして、劇作家が何を考えたかを知り、それを舞台の上で具現化するのが俳優であり演出家だというものです。僕はそこに最初から違和感があったというか、今でもずっと思ってるのは、演劇は文学に従事するものではない、演劇は演劇のために存在しているんだ、ということなの。それを具体的に形にするにはどうしたらいいか。その頃は演出家になろうなんて思ってもいなかったけど、僕らの近くにはそういう戯曲がなかったら、信さんや憐さんが書くわけです。すると“一所懸命書いたんだから、ちゃんとやってくれよ”という注文が増えてくる。それで仕方なく、演出めいたことをするようになっていったの(笑)」
──のちに佐藤さん、斎藤さんは、劇団黒テントを立ち上げられます。
「俳優学校の頃から、一緒にストリップ小屋に行ってコントを観たり、近い感性を持っているつもりでいたんだけど、やっぱり時間が経ってくると、どちらも少しずつ変わってくるんですよね。それが悪いと言っているんじゃなくて、何本も書いていけば自然に文体が生まれる。でも僕はもうちょっと……文字を超えたことにこだわってしまう。言葉ももちろん大切なんだけど、言葉を“意味”じゃなく“発する音”として捉えても演劇はつくれるんじゃないかとか、そんなことをずっと頭の中で──今も変わらずね──考えているんですよ。演劇って、本来はもっといろいろあっていい。シリアスに役に向き合って、その人物になりきってせりふを言うだけが演劇じゃない。歴史を考えていっても、もっとおもしろいものがたくさんあったはずだろうと、ずっと思っていたんですよね。きっとそれは、さっきの質問の最初に答えた、子供の頃に出会ったものの影響が大きいと思うんだけど」
──たとえばどんなものですか?
「小学3年だったと思うけど、今思い出してもおもしろい芝居だったなぁと思う劇を学芸会で観たんだよ。童話みたいな話なんだけどさ、時計の時間に人格があるの。夜中の1時、2時、3時に、それぞれの時間が出てきて議論しあうんだよね。“あっちの時間がわがままだ”とか、“こっちも大変なんだから、じゃあ入れ替わるか”とか。今ちゃんとやったら、結構おもしろい芝居になりそうだよね(笑)。
それと、中学に入ったら新入生歓迎会で、2年生が『うりこ姫とあまんじゃく』という劇をやってくれたのね。その学校がすごくてね、僕が入った時、長山藍子さんが2年生で、3年生に山本圭、東野英治郎さんの息子の東野英心と、あとから考えたらすごい顔ぶれ(笑)。で、僕ら1年生がおとなしく観てたら、後ろから先輩の生徒が野次を飛ばすの、“下手くそ! 俺にやらせろ!”って。“怖いな、ガラ悪いな”と思っていたら、だんだん野次が激しくなって、とうとうその先輩が舞台に上がっちゃったんです。ワイワイもめているうちに先生が出てきて騒ぎを止めたんだけど、よーく見ると、その先生も生徒なわけ。“あれっ?”と思ったら、その人が騒いでいた生徒に"お芝居で主役になれなかったから拗ねて野次を飛ばしてるなんて、本当の天邪鬼はお前だ!"と言う、まるごと彼らのお芝居だったわけ」
――すごく凝ってますね、中学生の学校演劇なんですよね?(笑)
「要するに二重構造でさ、メタなの。中学1年で出会った演劇がメタだもの(笑)。その前がシュールな、時計から時間が出てきて議論しあう劇、もっと前に見た演劇の原風景が、終戦直後の疎開先の芝居小屋でしょ。この3つの経験だけでも、相当深いところへ連れて行かれちゃった(笑)。それからは、中学、高校と背伸びして、ひとりで俳優座劇場に行ったりいろいろな新劇を見てそれもおもしろかったんだけど、そういうものを忘れない気持ちはいつもどこかにあったんですよね。大人になって、アンチテアトルだとか不条理演劇だとかに出合ったけど、新しいというよりは“ああ、あの感じだ”と思っていました」

──串田さんの作品の根底に流れる遊び心の理由がわかった気がします。
「やっぱり、戯曲にがんじがらめになる人が多過ぎるんじゃないかな。たとえばブレヒトは、僕も若い頃に頑張って読んだけど、書物としてはつまらないですよ。いろんな人が解説書いているんだけど、それを読んでも納得できなかった。いくら“叙情的”とか“異化効果”とか言われても、当時は生意気だったから“へーえ”って反発したし(笑)。それが1969年に東ベルリンに行く機会があって、まだブレヒトが亡くなって10年ちょっとしか経ってないから、本人の演出を踏襲した『三文オペラ』や『アルトロ・ウィの興隆』を観たら、これが物凄くおもしろかった。
叙情的でも難しくもないんですよ。客席もガンガン湧くし、“なんだ、ブレヒトって芝居好きのおっちゃんじゃん”という感じ。役者がものすごく上手いから、心理描写も細かいし、とっても色っぽい。観ながらグーッと惹かれましたよ。それで気がついたの。“異化”って、前提として観てるほうが相当惹かれていないと効果がない。熱を冷ますんじゃなくて、別の側面も見せることなんです。ブレヒトは、政治的な理由から表現活動が変化さぜるを得ないところもあったけど、本質はものすごく芝居が好きなおっちゃんだろうと。そういうブレヒトやれたらな、とその時から思っていたし、モリエールにしてもゲーテにしても同じように捉えています」
Text●徳永京子 Photo●源賀津己
くしだ・かずよし 1942年生まれ、東京都出身。俳優、演出家、舞台美術家。まつもと市民芸術館芸術監督。俳優座付属養成所、文学座を経て、1966年、斎藤憐、吉田日出子らとともに劇団自由劇場を結成(後にオンシアター自由劇場と改名、1996年に解散)。1985年から1996年まで東京・渋谷のBunkamuraシアターコクーン初代芸術監督を務める。2003年、まつもと市民芸術館芸術監督に就任。主な演出・出演作品にオンシアター自由劇場『上海バンスキング』(第14回紀伊國屋演劇賞団体賞受賞)、『クスコ』『もっと泣いてよフラッパー』など。コクーン歌舞伎、平成中村座の演出家としても知られる。
まつもと市民芸術館HP
『K.ファウスト』
10月6日(土)〜14日(日)
世田谷パブリックシアター(東京)
10月19日(金)〜21日(日)
まつもと市民芸術館 特設会場(長野)
『K.ファウスト』記者会見(9/27) の映像
『K.ファウスト』公開稽古(9/27)の映像