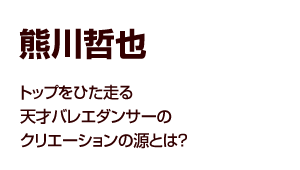「自分では高みに向かっているつもりでも、はたから見たら暗いトンネルに入っているように思えることがあるかもしれない。日常生活でそのギャップを感じることはあります」
――そういうとき、現実世界での熊川さんは?
「ちょっと休んで、愛犬と戯れたり。ムツゴロウさん状態でね(笑)。あとは集めている古書を眺めたり、好きなもの…家具や照明の配置を考えたり。窓から差し込む木漏れ日の具合が気になって“もうちょっとこんな感じで”と葉っぱを切ったりするのを、ひとりで延々とやっていることもあります(笑)」
――そんなところにも視覚と、視覚ではとらえきれないものとのこだわりが(笑)。ところで、先ほど霊的という言葉が出ましたが、続いて上演される『ベートーヴェン 第九』も、音楽という目に見えないものを視覚化するという点で、熊川さんの特徴が色濃く出ていると感じます。2008年初演の本作について、どのようなプロセスで着手されたのか改めて教えていただけますか。
「クラシック音楽はずっと身近な存在でしたけど、子どもの頃はクラシックといえば、すなわちバレエで踊る曲だと思っていたんです。そのうち、作曲家と振付家の共同作業でバレエの曲は作られているんだと分かってきたんですけど(笑)。でもそういう認識があったので、既存のクラシックで踊るというのは僕らダンサーにとってそう意外なことではないんです。それにベートーヴェンって、今でこそクラシックとひとくくりにされてますけど、発表された当時は前衛的というか、だいぶ型破りだったそうです。危険だとか、子どもに聞かせちゃいけないとまで言われたらしい。そういったこの曲のもつ気迫のようなものを感じて、僕は惹かれたんだと思います。無骨なカッコよさや、男らしい肉付けもいい。例えばモーツァルトが朝食用のサラダだとしたら、ベートーヴェンは分厚いステーキ(笑)」
――分かりやすいです(笑)。
「単純に男心をくするぐんですよ。同時に、第3楽章では“天の声のようだ”とも言われる繊細な美しさもある。実際のベートーヴェンは、名声欲の塊のような貪欲な男だったと思いますけどね。彼にとっては、難聴になったという悲劇さえアドバンテージだったんじゃないかと思うんですよ」
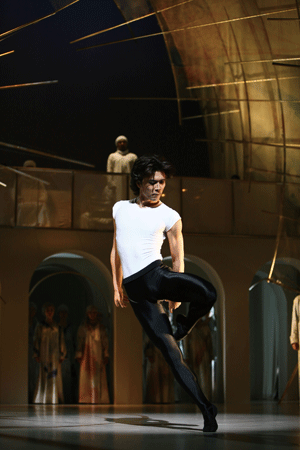
Kバレエカンパニー『第九』第4楽章より (C)Hidemi Seto
――そういう作曲家の創作物にぶつかっていくのは、相当なエネルギーが必要だったのでは。
「それは並大抵のものではなかった…ですね。特に日本では有名な、みんなに愛されているクラシック音楽ですよね。人間が成長する過程で多く演奏される特別な曲でもある、年越しとか。神秘性や哲学性を持ちつつ、現実的でもあり、そういう作品に僕がビジュアルという色をつけていくことの難しさを、調べていけばいくほど痛感することになりました。初めは単純にベートーヴェンに惚れ込むことから始まったんですけど、次第に、これは大変なことになったぞと。何億円規模のプロジェクトが台無しになってしまう怖ろしさもあって。それはこの作品に限らず、いつも感じていることではあるけれど」
――熊川さんは、手に入れられるものは古書なども実際に買ったりして、徹底的に調べるとお聞きしましたが。
「『第九』は1824年に初演されて、ベートーヴェンは1827年に死ぬんですけど、その前年の1826年には『第九』の楽譜が発行されていたんです。その初版はドイツのショット社というところから250部だけ刷られたんですが、ベートーヴェンが生きていた時代の空気をまとったものがどうしても欲しくて、そのうちの1つを手に入れました。ベートーヴェンの字は汚かったらしくて、清書して一度発行したものに間違いがあって…なんて色々な逸話があるのも面白いですよ」

Kバレエカンパニー『第九』 (C)Hirotsugu Okamura
――それを時折、取り出して眺めたり。
「本当に神々しく感じられる大切な楽譜です。オチを言っちゃうと、僕はオーケストラの楽譜は読めないんだけどね(笑)」
――そうなんですか(笑)。
「身近に彼の空気を感じるというのが大切だから(笑)。だって、この楽譜を実際にベートーヴェンが見て、もっときれいに刷ってくれよと文句を言ったかもしれないじゃない」
――(マネージャーが横から)でも熊川さん、オーケストラの音を一つひとつ聞き分けることが出来るんですよ。リハーサルのとき、「あそこの音がおかしい」とか正確に言ってらっしゃるのをよく見ます。
「昔からなんだ。こうやって話していても、すべての音が頭の中に入ってきちゃうんだよ。困るのは携帯電話で、こちらで話していて隣で別の人が話していると、2つの会話が同時進行してしまうこと。あとは振付のとき、ダンサーを見ていても音楽が鳴っていると、目の前で音が“動いて”いるのが“見えて”しまう。だから頑張ってダンサーのほうに注意を集中したり」
――“共感覚”(音に色を感じたりする特殊な知覚)という可能性も?
「はっきりと調べたことはないので、ただ落ち着きがないだけかもしれないけれど(笑)。でも音感はすごくいいみたいで、音に体で反応するんです。例えば他のダンサーと一緒に踊っていても、その人が音の一つひとつを聞いて踊るんじゃなくて型にはまったリズムの取り方をしていると、すごく気持ち悪くて。他にも、本を読んでいると一気に情報が入ってくるので、読みづらかったりということも」
――じゃあ古書収集というのは、読むほかに物体そのものを“感じる”ためでもある。
「そうですね。そういう大切な古書がいくつか自宅にあるんですが、古書を置いているだけでそこがパワースポットになるんですよ。日常生活で癒されながら充電するのは大切なことだと思います」

――古いものといえば、クラシックカーもお好きなんですよね。
「何台か持っているんですが、それぞれの細部にまでクラフトマンシップが感じられるのがいいんです。そういう車というのは語りかけてくるんですよ、こちらに。いつも同じ調子で乗れるとは限らないしね。車と向き合って、会話しながら乗るとでもいうか。デザインにしても僕らの祖父の頃のものなんだけど、心底カッコいいなぁって惚れ込んでしまうんです」
――19〜20世紀の古書や車と、熊川さんは同時代の人間のように共鳴しているように感じます。
「そういう物たちに触れていると、先人たちの声が聞こえる気がするんですよ。“お前、なにやってんだ”とか、“もっと何か出来るんじゃないのか”って。それは背中を押されるだけじゃなくて、迷っているとき、沈んでいるときに甘えさせてくれる声でもある。そういう過去の偉大な人々からヒントをもらって、もちろん現代のアーティストや新しい機械も視野に入れたうえで、これからもバレエを作り続けていけたらと思っています」
Text●佐藤さくら Photo●大久保啓二(熊川哲也)
くまかわ・てつや 1972年、北海道生まれ。10歳よりバレエを始める。英国ロイヤルバレエ学校に留学中の89年、ローザンヌ国際バレエコンクールで金賞を受賞。同年、英国ロイヤル・バレエ団に東洋人として初めて入団、93年にはプリンシパルに。豊かな演技力と高く滞空時間の長い跳躍で、『ドン・キホーテ』『海賊』を始め様々な演目で世界のバレエファンを魅了する。98年に退団後、翌年に自身のバレエ団であるKバレエカンパニーを創立し、芸術監督を務める。2003年にはKバレエスクールを設立。2012年1月、Bunkamuraオーチャードホールの芸術監督に就任。http://k-ballet.co.jp
熊川哲也 Kバレエ カンパニー Spring 2013『シンデレラ』
オーチャードホール (東京都)
3月6日(水) 〜 3月10日(日)
熊川哲也 Kバレエ カンパニー Spring 2013『ベートーヴェン 第九』
ほか
オーチャードホール (東京都)
4月11日(木) 〜 4月14日(日)
フェスティバルホール (大阪府)
4月20日(土)