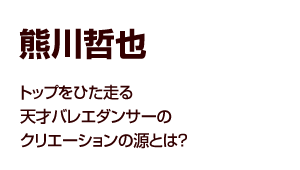この人がいなければ日本のバレエ界は語れない。熊川哲也、40歳。16歳でローザンヌ国際バレエコンクールで日本人初の金賞を受賞した彼は、英国ロイヤル・バレエ団で世界のトップに立った後、27歳でKバレエカンパニーを設立。古典作品に重きを置きながら、新作まで意欲的に手掛ける傍ら、バレエスクールを創設して子どもたちの指導にも熱心に取り組む。2012年からはBunkamura オーチャードホールの初代芸術監督に就任。昨年、その記念公演として好評を博した『シンデレラ』が3月に再び登場する。続く4月にはオリジナル振付の大作『ベートーヴェン 第九』も上演。そのクリエーションの源について、さまざまな質問を投げかけてみた。
――『シンデレラ』を記念公演の演目に選んだのはどういう理由からだったんでしょうか。
「我々はクラシックのバレエ団なので、上演するものといったらある程度は限られてくるんですね。その中で新作(熊川が演出・再振付するバージョン)を、というと数えるほどしかない。それなら『シンデレラ』をやりたいなと。『バヤデルカ』もいいかなと思ったんですが暗い情緒的な内容なので、最初は華やかな『シンデレラ』を選んだんです」
――Kバレエカンパニーの舞台は、クオリティはもちろん、バレエビギナーにも分かりやすいというのが大きな魅力です。『シンデレラ』で意識した部分はどこですか?
「バレエは言葉を使わないですから、観る人にもっと理解してもらいたいという気持ちはいつもあります。古典のいくつかは、つじつまが合わないというか、分かりにくさというのがどうしてもある。だからまずはストーリーの色づけと、物事をきちんと順序立てることに重きは置いてますけれど。でもそれは作品へのアプローチの仕方であって、それを優先しているわけではないんですよ。あくまでその他の要素…音楽と美術と、ダンサーの技量と、それら全ての相乗効果として作品を届けられたらと」

Kバレエカンパニー 『シンデレラ』 (C)Jin Kimoto
――熊川版の『シンデレラ』で具体的に“色づけ”した部分というと?
「例えば有名なフレデリック・アシュトン版の『シンデレラ』も、つじつまは合っていると思うんですよ。他の古典には、違和感を覚えるものもありますけど(笑)。だからいわゆる改訂版というのも、あくまで演出家個人のテイストであって、大きな軸から逸れずにスパイスとして枝道を出していくというのかな。ただ僕の『シンデレラ』はシンデレラの義姉たちだけでなく、義母を出すことで、それが自然と大きなポイントになった。誰よりも、何よりも自分がお姫さまになりたかった女性。その義母が策略を巡らすというのが、今回はプラスアルファの部分ですね」
――『シンデレラ』の義姉たちというと、コミカルな踊りが見どころですが。
「僕はコミカルというより、意地悪の部分を意識しましたね。でも最終的には、全ての登場人物が(観る人に)愛されなくちゃいけないと思うんですよ、僕は。本当に悪い役であっても、どこか哀愁が漂うとか。義姉たちにしても、シンデレラに意地悪し続けるのが愛のムチに見えたり。それは僕のいつも意識しているところです。アシュトン版などでは、割りと義姉たちはシンデレラに無関心なんですけど、僕の場合は1幕できっちりシンデレラをいじめますし。でも最後には観る人に温かい気持ちで帰ってほしいので、その収拾は考えます。そういう義姉たちの存在があるからこそ、対比としてハッピーエンドがとても明るく見えるというのもあります」
――シンデレラという女性はどうとらえていますか? シンデレラのソロでは1幕でお城への憧れ、魔法が破れて帰ってきての3幕では恋心の表現がありますが、ちょっと純粋すぎるというか、普通はもっと悔しい気持ちになるかと思うんですが(笑)。
「うーん…いや、純粋なんですよ、シンデレラは。純粋でなければいけないんです。そりゃ現実的に考えると、人が良すぎるんじゃないのと感じてしまうかもしれないけれど。純粋であって絶世の美女であるということ、王子が一目惚れするほどの女性であることが、バレエの基本設定なので。そこはね」

Kバレエカンパニー 『シンデレラ』 (C)Jin Kimoto
――そういう古典バレエの軸は残しておいて、同時に義母や義姉という、世の大部分の女性の気持ちも熊川版では描かれる。
「どちらも女性の本当の気持ちだと思うんですよ。その感情をどう出すかの違いだけで。女性はみんな“お姫さまになりたい”んじゃないかなと思います。例えば僕がロンドンに住んでいた頃、母が遊びに来たんです。それでウィンザーとかお城を観光してみようということになって。それまで母のそういった部分に触れたことがなかったので、初めて“あぁ、女性はみんなお姫さまになりたいんだ”って気がついた。そういうところは考えますよね。僕が女性の気持ちを分かっているかどうかは別として(笑)」
――(笑)。女性の役どころの話をうかがってきましたが、男性のダンサーについては、何か特別にアドバイスされたりとかはありますか。
「それはないです。ダンサーへは女性も男性も同じように接していますね。バレエはまず(技術的な)形式があるのでそれが出来てないといけないわけですけど、ある一定まで達したら、その先からが本当のスタートになるんです。そこからのプロセスが、ダンサーとしての個人を作り上げる非常に大切な部分。その高次なフィールドに達するためには、形式ではなく、より感性の部分…形而上的な意味での“霊的な”部分が必要になってくる。それを教えるといっても、言葉で伝わるとは限らないですから。これを観たほうがいいんじゃない?とか、これを読んでみれば?ってぐらいは言いますけどね。もちろん感受性が豊かであっても、形式が出来ていなければ何にもならないし。神から与えられた体の形成と、育った環境も含めた人間形成のプロセスが上手くマッチングしないと」

『シンデレラ』リハーサル風景より (C)Ayumu Gombi
――具体的にはどういうものを勧めることが多いですか? 美術や本など?
「どれというより、とにかく多くの芸術作品に触れてほしいとは言いますね。自分で観て、体験して、自分の中で消化していかないと意味がない。例えば20世紀初頭の“バレエ・リュス”(セルゲイ・ディアギレフが主宰したバレエ団)は、振付家のほかに、ピカソやストラヴィンスキーなど画家や詩人、音楽家たちが集まって花開いたもの。それを知っていれば、ダンサーも音楽や美術と調和しながら舞台に立つということが段々分かってくる。そういう、自分で探し当てた“宝物”を一つひとつ取り込んでいくということだよね。人からもらった“宝物”じゃ、価値が全然変わってきちゃう。そして、その取り入れたものをパァーッと表現できる子というのは、小学生でもいるんですよ。逆に、萎縮しちゃってなかなか殻が壊せなかった大人が、何かをきっかけに劇的に変わることもあるけれど」
――それは、バレエスクールを始めてから分かったことですか?
「いや、こういうのは僕自身の経験で感じてきたことです。いろんな所でいろんな経験をして、それを肥やしにして出来上がった、ひとつの世界観が僕の中にある。それを感じながら踊るのと、そうでないとでは喜びが違います。ただ、やっぱり感受性が伴って踊るほうが自分に正直でいられるし、誇りをもってお見せできるという確信がありますね」

『シンデレラ』リハーサル風景より (C)Ayumu Gombi
Text●佐藤さくら Photo●大久保啓二(熊川哲也)
くまかわ・てつや 1972年、北海道生まれ。10歳よりバレエを始める。英国ロイヤルバレエ学校に留学中の89年、ローザンヌ国際バレエコンクールで金賞を受賞。同年、英国ロイヤル・バレエ団に東洋人として初めて入団、93年にはプリンシパルに。豊かな演技力と高く滞空時間の長い跳躍で、『ドン・キホーテ』『海賊』を始め様々な演目で世界のバレエファンを魅了する。98年に退団後、翌年に自身のバレエ団であるKバレエカンパニーを創立し、芸術監督を務める。2003年にはKバレエスクールを設立。2012年1月、Bunkamuraオーチャードホールの芸術監督に就任。http://k-ballet.co.jp
熊川哲也 Kバレエ カンパニー Spring 2013『シンデレラ』
オーチャードホール (東京都)
3月6日(水) 〜 3月10日(日)
熊川哲也 Kバレエ カンパニー Spring 2013『ベートーヴェン 第九』
ほか
オーチャードホール (東京都)
4月11日(木) 〜 4月14日(日)
フェスティバルホール (大阪府)
4月20日(土)