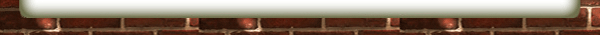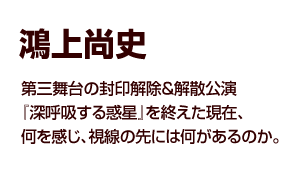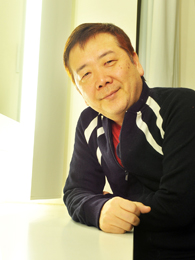
10年間の封印を解く久々の公演が、そのまま解散公演になってしまった……。時代に敏感に反応する瞬発力と、多様なカルチャーに接続する柔軟さで、小劇場のイメージを更新した第三舞台。その存在はまさに、あらゆる層を巻き込む社会現象だったといっていい。果たして解散という選択の裏に何があったのか。区切りに際し、現在・過去・未来を語ってもらった。
――『深呼吸する惑星』の公演最終日の様子は、全国30の映画館で生中継されました。5500人がスクリーン越しにラストを見届けたそうですが、上演地となった福岡・キャナルシティ劇場はいかがでしたか?
「地元の公演関係者によると、“今日のお客さん、半分ぐらいしか福岡の人いませんよ”って。あとの半分は、全国あっちこっちから、大千秋楽を見届けようと思って来た人みたいです」
――カーテンコールでは、鴻上さんとキャスト全員によるあいさつがあって、さらに、幕をスクリーンにして特別な映像が映し出されましたね。すべての上演データと"第三舞台を創った人達"を列記したエンドロールで、最後に“And”“You”の文字……。その後も、拍手、手拍子が鳴り止みませんでした。
「“And”“You.”のエンドロールで、もう絶対終われると思ったんだよね。本来『深呼吸する惑星』で緞帳は下ろさないんだけど、最後だけは、客席の明かりがつくと緞帳が下りているようにしようと考えて。これでまあ終わるんじゃないの? って舞台監督と話してたんだけど、終わりゃしない終わりゃしない(笑)」
――で、いよいよ鴻上さんが登場して、こう言ったんですよね。「ちゃんと終わらなきゃ、ちゃんと始められないよ!」と。
「はい。あれ瞬間的に良いこと言ったねえ! 自分でも“こんなとっさに良いこと言えた!”と思って。ハハハ」
――思い起こせば、映画館での上映も第三舞台が先駆けです。『朝日のような夕日をつれて'91』のクローズドサーキットをスタジオアルタで行ったんですよね。
「そうでしたね。一番最初にやりました。技術的にも経費的にも今より大変でしたけど。なんか途中電波が乱れたけど、パラボラアンテナにカラスが止まったのが原因とか(笑)、冗談みたいなことを中継スタッフが言ってたりしたから。でも今は、光通信でできるから。時代は変わりましたね」
――大千秋楽の打ち上げはどんな感じでした?
「水炊きのお店で、全スタッフと役者で。いい打ち上げでしたよ。というのは、普通、大入り袋をプロデューサーが配るとき、メインどころだけがあいさつして終るものなんだけど、気がついたらスタッフ30人ぐらいいたのがそれぞれ全員コメントしていたんだよね」
――宴は朝まで?
「次の日の飛行機が午前中だったので、結局3時ぐらいに終わったっていう感じかな。スタッフは朝9時から劇場のバラシがあったし。最後は屋台でした」
――鴻上さんがあいさつして締めた、と。
「ううん。別に“帰ろか”っつって」
――さらりとしてますね。
「まあさらりっていうかね、なんだろうなあ。俺たち、5周年の時も“5周年と1か月記念”みたいな祝い方をして、要はその、真っ当にベタをやることがやっぱり恥ずかしいし、野暮だと思うところがあるんだよなぁ。当たり前なことを当たり前にやってもしょうがないんじゃないか、みたいな。だから本当は、千秋楽も何もなく普通に終わりたいんだよ。別に好きで盛大にやっているわけじゃない」
――お客さんのため。
「それもあるしね、だってそもそも、作品で伝えてるわけだから。それ以上はもういいだろうっていう感じなんだよね。うん」
――その大千秋楽が今日から10日前でしたが、それからはどういう毎日を過ごしていますか。
「今は、次の芝居……次っていうか、具体的に明確に言えないんだけど、ある芝居を準備するためのシノプシスを今一生懸命書いてるところ。そのシノプシスを書きながら、書籍の校正をしているのがメインかな」
――そんな日々の中で、“解散した”という実感はあるんでしょうか?
「うーん、まあ、やっとひと区切りついたかなって感じですね」
――虚脱感のようなものは?
「すごいガクッとくるかなとか、呆けたようになるかなと思ったらそうでもなかったんだよね。それこそ飲み会の時もそうだけど、"ここからどうするか"っていうことのほうを一人ひとり思ってるんだなと。"あぁなるほど、やっぱり区切りをつけるっていうことは、もう後ろを見るってことじゃなくて、前を向くっていうことなんだな"と。だから思ったほど虚脱感もなければ、終わったんだなっていう感慨もなかったんだよね。うん」

――ところで、『深呼吸する惑星』は解散とリンクした作品という理解でよいのでしょうか?
「どうだろうなあ、それは。自分でも想像できないねえ。つまり、解散じゃない場合に書いてないので。解散公演じゃなくてもこれを書いたかどうかっていうのは……ちょっとわかんないよねえ。どうなんだろう? でもやっぱりその時の役者および僕のコンディションがまるごと投影されるのがやっぱり劇団だと思うんだよね。投影されすぎてもまずい時はあるし、といって全く投影しないのもやっぱりまずい。そういう作家さんもいますよ、世の中には。つまりどんな構成員であろうがとにかく自分の世界を書き続けるっていう。だったら劇団じゃなくていいじゃんっていうのがあって。といって、劇団の状況に引っ張られすぎて単なる劇団版私小説みたいになるのも面白くない。その危ういバランスの中で、何が面白いのだろうかと思って書くんだよね」
――スクリーンで観た大千秋楽の演技は、公演開幕当初の11月と比べてさらに練り上げられていました。
「進化したなと、表現するスキルが上がったなとあらためて思いましたね。東京公演と比べたら随分、セリフに重みや深みが出た」
――キャリアの長い、あのクラスの俳優さんでも“伸びしろ”があるんですね。
「いやいや、逆にあのクラスだからあるのかもしれない。やっぱり人間だから、最初からいきなりドーンといくというよりは、毎日毎日徐々に深まっていくんじゃないかって気がしますけどね」
――ギャグの威力もアップしていました。当初“ムチャぶり”とも思えたギャグに対しても、役者さんが確実に芯をとらえるようになったというか。
「微妙な範囲で手に余ることをお願いすると、俳優って伸びるんだよね。手に余るそのさじ加減は、見極めなきゃいけないんだけど。あまりにも手に余ると俳優を潰すし、といって手に余らない範囲だけのオーダーを続けていると俳優は伸びないよね。プロデュース公演だと難しくて、ムチャ過ぎで心を閉じてしまわれても困るから、結果臆病になってしまうというか、ムチャを振らなくなってしまう。やっぱり劇団だからそれができるっていうのはあると思う」
――ところで、『深呼吸する惑星』では、選曲についての問い合わせが多かったようですね。
「ブログに曲目リストを書いときゃみんなが見て終わるんだろうけど、ツイッターっていうシステムは、書いたことがどんどん下に消えていくので、何度も訊かれて、“また書くんかい!”っていう(笑)」
――斉藤和義さんの曲が印象的でした。
「表裏(『ずっと好きだった』『ずっとウソだった』)両方使わせてもらいました」
――既存の楽曲を厳選して劇中に使うというのは、やはり鴻上さんが先駆者ですよね。
「昔から、音楽にはこだわってきましたね。本当は作曲家さんに曲を書いてもらうのが筋なんだと思うんだけど。僕が好きなアーティストであっても毎回名曲が書けるとは限らないっていう厄介な問題があって。といってせっかく作曲してもらったものに対してダメですとはなかなか言えない。だから、ここ一番っていうか、肝心のキモの場面の曲に関しては、芝居のイメージとオーバーラップして、芝居のイメージをもうひとつ膨らましてくれるようなものを、有り物の中から僕が選ぶほうがハズレがないんだよね」
――30年前の話にいきなり飛びますが、当初、第三舞台は劇団として何を目標としていたのでしょう?
「第三舞台の目標ってのはつまり、自分たちが観たい芝居を作るっていうことでした。どの芝居を観に行っても、帯に短しタスキに長しで、最初はすごく面白くても、途中からつまんなくなるとか、全部が面白いっていうのがなかったので。“俺たちは、とにかく頭からケツまで全部面白いのを作ろうぜ”と思ったわけです」
――ショウビズ的な成功は目指していたんですか?
「もちろん、演劇で食おうとは思ってたけど、ショウビズとしての目標はあまりなかったよね。要は俺たちが面白いと感じるものをやれば、お客さんがたぶん集まってくれて、その結果として、食べられるようになるんじゃないの? っていうなんとなくの読みはあったけど。まずはとにかく自分たちが徹底的に面白いと思うものを作ろうぜっていうことが一番でしたよね」
――ということは、既存の演劇に対しては“アンチ”だったわけですね。
「新劇に対してはアンチだったけど、それよりは、劇評を読んで絶賛されている芝居を観に行って、心から、ああ本当に高評価に値するなぁってことがあんまりなかったんだよね。なんでこれが褒められてるんだろうと。だったら俺たちもっと面白いことできると思うけどなぁ、とすごく思ったわけだよね。当時、コメディとしてすごく面白い芝居があり、それからシリアスな新劇の問題作があったりしたんだけど、俺なんかは、自分の人生の実感として、笑いだけじゃつまらないし、深刻なだけじゃやってられないし、重いことと軽いことが同時に存在している芝居をとにかく作りたいと思って。悲劇と喜劇が同時に存在してる芝居っていうのが本当になかったんだよね」
――では、独自の作風を追求した結果、人気が出たんですね。つまり、売れようとして売れたのではなくて。
「ああ、うん。それは全然ないね。売れようとして売れたっていうのはない。そこは今でも自分自身を戒める部分だけど、結果として売れてしまったから、どうも商売的にはあんま上手くない(笑)。やっぱりそれは、後にオーディションで入ってきた組の筧(利夫)とか勝村(政信)とかを見ると、売れることの大切さをすごいわかってるなと。だけど大高(洋夫)とか、まして小須田(康人)とかそうだけど、呑気組なんだよね。やっていれば、結果として売れるんじゃないの?っていう意識があるわけ。だから今でもプロデューサーとかにたしなめられるんだよね。たとえば俺が“これだけキャスティングしたらもういいでしょう”って言うと、売れるっていうことのためには“もう一枚、有名どころを入れておいたほうが絶対いいですから!”みたいにして。売れることに対する貪欲さ、ショウビズの厳しさに関しては、すごい呑気なんだよね」
――やがて人気の頂点をきわめる劇団の当事者が、商業的な成功に対して無意識だったとは意外です。
「その無意識がかえって良かったんだと思う。そういえば今回、紀伊國屋ホールの楽日の後、筧にダメ出しされたんだよね。カーテンコールが終わってもなかなか拍手が収まらなくて、こちらとしてはあらゆる手を尽くしたし、そこで終われると思っていたものだから、すごくアタフタしてしまった。で、俺なんかはそのアタフタが結構いいなと思ってたんだけど、筧にはもう"ダメです! こんなのはエンタテインメントじゃないっす!"とか言われて(笑)」
――スマートじゃない、と。
「確かに、エンタテインメントじゃないって言われたらそうかもしれないなと。こればっかりは、なんだろう。自分で言うのもなんだけど、第三舞台って奇跡が起こったんだと思うんだよね。つまり、売れようということを一番にしなくて、自分たちのベースっていうか実感を元に芝居を作ろうっていうふうにしたことが、結果として多くのお客さんに届いたんじゃないかっていう感じがするな」
――戦略より、まず衝動。
「だったと思うなあ。本当に何をやりたいのか。それを自分たちで自分たちに問いかけ続けたっていう感じだと思う」
――そのモチベーションは30年間変わりなく?
「そう。たとえば今回第三舞台をやろうと思ったのは、40代後半から50代になったやつらが、どういうふうに生きていくのかっていうことを書きたかったし、一緒にやりたいなと思ったからで。それがなければやらなかったと思うんだよね」

Photo●源賀津己
こうかみ・しょうじ 1958年生まれ、愛媛県出身。作家/演出家。1981年に第三舞台を旗揚げし、小劇場ブームの中心的存在として時代をリードする。第三舞台は、『深呼吸する惑星』(2011年11月〜2012年1月)をもって解散。演劇を始め、映画、ラジオ、エッセイ、小説等幅広く活動。最新著書は『演技と演出のレッスン』(白水社)。演劇公演としては、6月からザ・ブルーハーツの楽曲を使った音楽劇『リンダ リンダ』を上演(紀伊國屋サザンシアター、他)する他、2012年は「虚構の劇団」としての活動も予定している。
サードステージ公式ページ
KOKAMI@network vol.11
『リンダ リンダ』
6月20日(水)〜7月22日(日) 紀伊國屋サザンシアター(東京)
7月28日(土)〜30日(月) 森ノ宮ピロティホール(大阪)
※東京公演は4/21(土)、大阪公演は5/26(土)に一般発売。
【BOOK】
『演技と演出のレッスン
魅力的な俳優になるために』
白水社 1890円