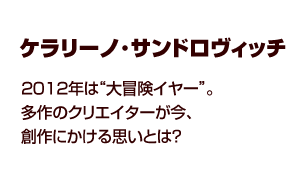昨年も『黒い十人の女』『奥様、お尻をどうぞ』と話題を呼ぶ作品を上演してきたケラリーノ・サンドロヴィッチ。主宰する劇団・ナイロン100℃の公演のみならず、毎年さまざまなユニットやプロジェクトを次々と繰り出しては私たちを楽しませてくれる、演劇界に欠かせない存在だ。その彼が自ら“大冒険イヤー”と名付けた今年、いったいどんな企みを? と問おうとすれば、取材場所に現れた当人は、生みの苦しみに頭を抱えていた……。
――2012年1作目はオリガト・プラスティコ『龍を撫でた男』ですね。昭和27年初演というこの福田恆存の怪作に、どのように出会ったんですか?
「ちょうど昨年『黴菌』をやっていた時、山崎一さん演じる精神科医の役を描くにあたって資料を探しているうちに見つけました。今回のキャスティングはほとんど広岡(由里子)が決めたんですが、山崎さんはまた精神科医役なんですよね」
――いまは稽古真っ最中だと思いますが。
「他人の脚本でこんなにも苦しんだことはないですよ。今日の稽古でも広岡に『ここまで細かいことを言われたのは生涯で初めてだ』と言われました。オリガト・プラスティコは広岡ありきでできたユニットなので、毎回広岡にどんなことをさせようかということが最初の目標になるんです。彼女はすごく照れ屋で、いわゆる女優!という感じの、例えば『欲望という名の電車』のブランチに代表されるような狂女の役を率先してやりたがるような人ではない。そこを引っ張り出して狂気を演じさせるというのが今回の大きな目標なんです。まあ狂っているのは広岡の役だけではないんですけどね(笑)」
――その狂気を引っ張り出すところに苦しんでいる、ということですか?
「役者が役を演じるにあたってのよりどころが漠然としている脚本なんです。あまり筋を通そうとしすぎては、成立しない台本でもある。自分をコントロールできない人たちの物語ですから。あとは、笑いを狙った芝居じゃないのが難しい。いや、笑いは笑いでもちろん大変だけれど、なにしろ慣れてますからね、笑いの舞台は。こうしたら客が笑う、笑わないというのは判断がつくんです。そうじゃないところでどんなやり方を選択していくか。もうこれでいいよってOKを出してしまえばそれなりのものになるだろうし、面白いと思う人だってたくさんいるかもしれない。でも、2、3年前ならOKが出せたラインでも、今は出せないというのがありますね」
――かなり高い位置にハードルがあるということでしょうか。
「そうですね。今回は思い描いている演技トーンがあるんです。ステレオタイプな、狂騒的なだけの芝居で終わってしまいたくない。すれ違いや噛み合わなさが笑いに帰結するというのは僕の得意分野ですけども、それが笑いではなく怖さやいら立ちに結び付くような、意見ではなく状態がすれ違っていくようなことをやりたいし、作者は意図していないと思いますがそれができる脚本なんですよね」
――Twitterで、今年は大冒険イヤーであるという宣言をされていましたね。
「年々自分のスタイルが確立されて、近年の劇団の公演では毎回クオリティの高い作品を作れているという自負はあるんです。ナイロン100℃の主要メンバーも非常に手堅いブレのない芝居をしてくれている。ただ、その一方で、完成されてしまっているのではないかということが不安でもあるんです。完成されちゃったら、もうそれ以上完成することはない。ナイロンを始めた時に作っては壊すことを毎回続けていくという気持ちだったのに、はたしてこれでいいのかなと。まあ、これはあくまでも僕の中の問題で、はたから見ていると危なっかしく見えたり、いろんな冒険をしているように見えるかもしれないけれど(笑)。だから今年は、今まで避けてきたようなリスキーなこともどんどんやろうという宣言ですね。後先考えずに無茶しよう、あまり安定しないでいこうという気構えで1年を過ごそうと思っています。来年は50歳になっちゃいますし」
――ご自分の年齢はかなり意識されますか?
「しますね。30歳過ぎたころから『あと何本できるんだろう』とカウントダウンをしている。もっとも、『何本できるかわからないから闇雲にやろう』という時期と『何本できるかわからないから一本ずつ丁寧にやっていこう』という時期と、気持ちはいろいろ変わっていくんですけど」

――2011年を振り返ると、Twitterでのつぶやきが反響を呼んで実際の上演に結びついた『黒い十人の女』や、テレビでは絶対にできないような内容の『奥様、お尻をどうぞ』と、冒険的な作品が続いていた印象があるのですが。
「『黒い十人の女』や『奥様、お尻をどうぞ』は、始まる前から観客の食いつきはいいだろうなという確信があるんです。"市川崑原作の超スタイリッシュな映画を舞台化"とか"古田新太と組んでテレビでは絶対放送できないようなデタラメなことをやる"とか、分かり易い話題性があって、ひとことでいえばキャッチーな公演。でも今年やる3本の作品は、そういう売り文句を作りづらい。パッケージとして地味なんですよ。今までもそういうものを避けてきたわけではないけれど、ものすごく派手な作品をやった後だからこれぐらい地味でもいいだろう、とバランスを考えてやってきた。そこを今回はプロデューサー的な視点を持たずにやってしまおうと」
――そう思うに至ったきっかけが何かあったんでしょうか?
「うーん、震災の直後から昨年いっぱいぐらいまでは、僕にも“暗いものは見たくない”という気持ちがあった。『奥様〜』は作品というよりも運動のようなものでした。みんながデモをやる代わりに僕らが芝居をやった、そんな気がします。作り手である以前に同じ日本の国民として共有するものを考えた。今も、どんよりするようなものは見たくない人もいっぱいいると思う。だけど、なぜか今はコメディを作りたいっていう気分ではないんです。それは去年の『ノーアート・ノーライフ』でもうしばらくいいんじゃないかっていう思いになっている。だから、今年の3本に関しては、お客の笑い声が皆無ってことはないでしょうけど、コメディ作品としてつくるってことから離れたい。地味でシリアスな作品は歓迎されないかもしれないけれども、とにかく今自分が面白いと思うことをやりたいんです」
――ただ、これまでとは違った作品が見られるという意味ではKERAファンは3本とも見逃せない作品になりそうですね。
「3本を通して見えてくるものもあると思うし、今年のこの覚悟は尋常ではないので、ぜひ3本とも観てほしい。本当に来年があるかどうかという気持ちなんですよね。というか、ここで頑張ってダメだったら、一旦5年ぐらい休んでもいいんじゃないか」
――5年も休んだら演劇界はきっと相当困りますよ。
「演劇の公演スケジュールってだいたいいつも2年先まで決まってる。でも人間、いつ死ぬかなんてわからないじゃないですか。もし死んだり病気になったら、当然ながらその2年間の予定はキャンセルすることになるわけですよね。だったらもしかして、キャンセルしてしまうのもアリじゃないかと……。スケジュールが空いたところはみんなに生前追悼公演でもやってもらえばいい(笑)」
――KERAさんは関わらずに、ナイロンのメンバーがセッションを重ねていくならば、それはサイドセッションになってしまいますね((笑)。2月の『持ち主、登場』でサイドセッションもVol.10になりますが。
「昨日、心配で大倉(孝二)にメールしたらまだ台本が1ページもできてないっていう返事がきましたよ。『持ち主、登場』に僕は全く関わらないけれど、一回たまたま路上で大倉に会って、これから打ち合わせだっていうから僕も行ってみたんですよ。そしたらみんなに妙に緊張されてしまって……3分も経たずに帰りました。まあ、でたらめな芝居ならばなんとでもなる。僕も『奥様〜』のとき、間に合わなかったら途中で終わらせようと思ってた。でたらめはどこで終わらせてもいいから(笑)」

Text●釣木文恵 Photo●源賀津己
ケラリーノ・サンドロヴィッチ 1963年、東京都生まれ。ニューウェーブバンド・有頂天のフロントマンとして、また自主レーベル・ナゴムレコードの主宰として名を馳せる。1985年立ち上げの劇団健康を経て、1993年にナイロン100℃を旗揚げ。2003年『1980』で映画監督としてもデビュー。以降、劇作家、演出家、映画監督、ミュージシャンと幅広いジャンルで活躍している。