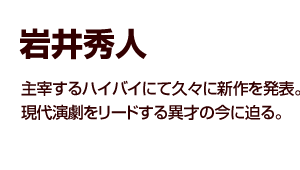――なるほど。では次に『ある女』についても伺いたいんですが、岩井さんは家族や身近な人に取材をして台本を書くことが多いですよね。今回もテーマになっている不倫の話は取材した事実に基づいているんですか?
「そうですね。何を書くかそんなに決めてない時に、知りあいづてで不倫しかしてない女性がいるって聞いて興味を持って。実際3人に取材したんですけど、そのうちふたりがそうでしたね。多分、僕が知らないだけで、不倫している女性の潜在的な人数って半端ないと思うんですよ。社会的にはよくないこととされてるし、芸能人が不倫するとすごく怒られるけど、不倫してる人のパーセンテージはすごく高い。ってことは、どっかで隠れながらやってるはずで、その"隠れながら"っていうのがどこかおもしろそうだなって思ったんですよ」
――取材の中で出会った面白いエピソードは例えばどんなものがありました?
「2人目に取材した人だったんですけど、既婚者じゃないと経済的な感覚がしっかりしてないからダメだよっていう考え方なんですね。で、会うたびに何かをもらったり、どっかに連れて行ってもらったりしている。それを続けてるうちに、彼女、これはちょっと自分の価値をあげなきゃ相手に申し訳ないと思って、セックス(指南)教室に行ったらしいんですよ(笑)。この間僕も実際に行ってきたんですけど、めちゃめちゃおもしろかった。それだけでほんとは一本作りたかったんですけど、そうするとセックス教室の話になっちゃうからやめましたけど」
――実際、台本を読ませて頂いて、そのくだりは最高に面白かったです。
「台本に書かれている通り、セックスを指導する職業があるんですよね。粘膜の接触はないんだけど、真っ裸になって、手を触ったりして、"もうちょっとソフトでもいいと思いますよ"とか指導してもらう。聞いたら、もう8年くらいその仕事やってるっていうんですよ、その人。ちょっと取材できないですか?って言ったら、厳しいですねって言われちゃったんですけど(笑)」
――家族の話を書く時も、実際にお母様に取材をされたりしてましたけど、やっぱり、人から実際に聞いた話をベースに作品を作るのが性に合っているんでしょうか?
「そうですね。人の話を聞くのが楽しいんですよね。“その人がこういう状況でこういう判断をした”っていうのが面白いから、それをそのままお話にしたいと思っちゃう。おれがこう思ったとかっていうよりは、人の行動や心理に興味があるんです」

2011年10月には、ハイバイの代表作『ヒッキー・カンクーントルネード』を韓国で上演 (C)松本大介
――逆に今後、完全にまっさらな状態からフィクションを立ち上げるっていうことは考えていない?
「いやー、まったく想像できないですね」
――言い換えると、取材に基づいて書く限り、ネタは尽きないっていうことですよね?
「そうなるといいなあと思いますね。色々な人に話しを聞いて、それをさも我がごとのように話せるようになるといいなって。ただ気をつけているのは、最終的には言葉が先に立つんじゃなくて、体感に落とし込むようにするということですね」
――確かに、『て』の組体操のシーンでも、『ヒッキー』のプロレスのシーンでも、重要な場面でフィジカルに着地させる傾向はありますよね。
「そうです。だから、言葉言葉しないようにっていうのは気をつけていて。『ある女』も初稿は読み物みたいになっちゃったので、今、台本もかなり言葉を削っていますね」
――ところで、最近小説を書かれているそうですね。以前は、ひとりで完結させる作業は苦手だから無理だと思うとおっしゃってましたが。
「そうなんですよ。前は、3ページ書いたらそれを持って、稽古場に行ってみんなでわいわいやるような環境じゃないと耐えられなかったんですけど、今は隅から隅まで思い通りに指定できるっていうのが面白くて。あ、できるんだって自分でも驚いてます。昔は、あんな寂しいこと絶対できないなって思ってたし、1、2ページで死んでましたからね。たぶん、『四つ子』をやったことが大きいと思うんですよ。それぞれ個性が違いすぎるから、他のやつらうるせーなと思ってたんじゃないですかね?(笑) 他人めんどくせー、みたいな(笑)。その反動で小説が書けているのかもしれない。その意味でも、『四つ子』は色んなものを産んでくれましたね」

Text●土佐有明 Photo●星野洋介
1974年生まれ、東京都小金井市出身。2003年にハイバイを結成。〈東京であり東京でない小金井の持つ、大衆の流行やムーブメントを憧れつつ引いて眺める目線〉を武器に、家族、引きこもり、集団と個人、個人の自意識の渦、等々についての描写を続けている。2007 年より青年団演出部にも所属している。
ハイバイ公式HP