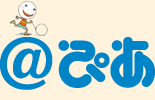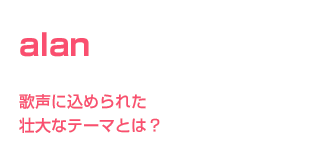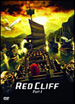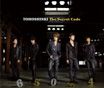![]()

Text●木村由理江 Photo●幾石倫子
スタイリング●鈴江英夫 ヘアメイク●岩城舞
![]()
『レッドクリフPartII -未来への最終決戦-』の全世界主題歌『久遠の河』での圧倒的な歌唱力とPV映像から勝手に創り上げていた“alan=成熟した女性”のイメージは、実際の本人と話すうちに微笑ましく覆された。日本語や日本の文化にまだ十分に慣れていないということも多少はあるだろう。でもなにより物事の捉え方が真っすぐ。デビューから1年半、21歳のalanの少女のようなかわいらしさに触れて、歌声がまた魅力的に聴こえてきた。
――『久遠の河』も収録された1stアルバムの『Voice of EARTH』。デビューの頃から“愛と平和と地球環境”をテーマにしているalanさんらしいタイトルですね。
「最近の天候からもわかるように、地球の環境はどんどん悪くなっているし、地球は今、すごく苦しんでいると思う。地球は声を上げられないけど、その声に耳を澄ましてほしいという想いで作ったアルバムです。私は身体も小さいし細いし力もないでしょ(笑)。何もできないけれど、歌うことはできるから、私の歌声で愛と平和の大切さや、地球環境への意識を高めてもらえたら嬉しい。それが私の使命だと思っています」
――『久遠の河』を最初に聴いた時にはどんな印象を持ちましたか?
「とても壮大なバラードだと思いました。あと、私が歌わせていただいた、PartIの全世界主題歌だった『RED CLIF〜心・戦〜』よりも、強さや未来への希望が感じられる曲だな、とも思いました」
――冒頭のフレーズから、平和が訪れたイメージがありますよね。
「一緒に戦っていた人たちも、戦争が終わるとそれぞれの国に帰るから別れ別れになる。それはちょっと寂しいけれど、二度と会えないわけじゃない。また会いましょう、という想いを込めて、明るい気持ちで歌いました」
――最初のサビでは最後のフレーズが“生きてゆける”なのに、最後のサビでは“生きてゆこう”になっているところにも、希望や力強さを感じました。
「サビは3個ありますが、最初のサビよりふたつ目、ふたつ目より最後のサビ、というふうに気持ちが強くなっていっています。最後のサビでは、この先何があっても絶対に生きていってみせる、という強い決心を歌で表現しました」
――それについては、ジョン・ウー監督からのアドバイスもあったようですね。
「最初にレコーディングしたデモテープを監督が聴いて、『すごくいいけど、最後の“生きてゆこう”だけはもっと明るく、力強く歌ってほしい』と言われました。映画の最後半の別れのシーンに気持ちが引っ張られて、ちょっと寂しい感じで歌っていたので。監督だけでなく、映画のいろんなスタッフが、歌の意味やどんな気持ちで歌えばいいかを、指導してくださいました」
――教わったたくさんのことを全部消化して歌ったわけですね。
「実際に歌い始めたら、歌に入り込んで想いを込めて歌うだけですけどね」
――今回の歌は、“愛と強い信念、そして勇気”がテーマだそうですね。
「テーマは映画と一緒です。映画には戦いの場面がいっぱいあってちょっと怖いところもあるけど、観終わったあとには愛と平和の大切さが心に残ると思います。なぜ人が戦争に行くか? それは愛する家族を守るため。そのために相手を倒してやる!という強い信念で向かっていくんですよね。家族と一緒のときと敵を傷つけようとしているときの顔は、別人のような表情だし」
――戦争の根っこにあるのは愛する人を守ろうという優しい気持ち・・・。“戦争”は難しいですね。
「戦争も、人生も難しいですよね」
――人生の難しさを、感じているんですか!?
「時々、感じます。基本的にすごく恵まれていて、お仕事も楽しくできているんですが、時々友達がいない寂しさを感じたり、日本の文化との違いに戸惑ったり、日本語の難しさに悩んだりします」
――でも困難にぶつかっても越えていく強さを、alanさんはもっているんですよね。
「あまり深く考えないようにしているし、悩んだらすぐに寝ちゃいます(笑)。でもどんなことでも乗り越えていける方法があるとは思います。ステージに出て行ったら誰も守ってくれないけれど、いつも支え、相談に乗ってくれるスタッフがいてくれるし。時々『今日は頑張ったから、おいしいお肉を食べに行こう』と言ってくれる。私もそれですぐに元気になります。そういうところ、まだ子供なんですよね(笑)」
――alanさんの歌声が世界に届いていくのは、今回が2度目になりますね。
「本当にとても光栄なことなので、一生懸命心を込めて、大切に歌いました。国や言葉や人種は違っても、みんな同じ地球に住んでいる家族。それを私の歌で伝えられたら嬉しいですね。人は誰もが愛されたいと思っているんです。だから“自分から愛する勇気”を、少しずつでいいから、みんなで身につけていきたいですよね」
デビューからちょうど1年 日本での活動で得たものは?(2008年11月27日インタビュー)