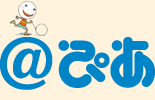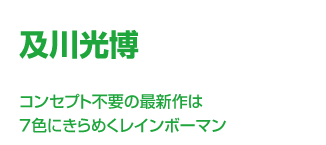![]()

ミュージシャンとしてだけでなく、この人が俳優として、しかも長きにわたって活躍し続けているのは多くの人が知るところである。そこで、この人が音楽活動を二の次にしたことはこれまで一度たりともない。定期的に新作を発表することを忘れなければ、大々的な全国ツアーも毎年実施している。だからといって俳優業を片手間にこなしたことなど一度たりともない。さて、そのミッチーこと及川光博。恒例ともいうべきツアーのキックオフを12月に控え、『RAINBOW-MAN』なるタイトルのアルバムを発表した。多忙の中で完成させたこの作品、そしてタイトルに込めた思いについて、本人にたっぷりと語ってもらった。
Text:島田諭、Photo:三浦孝明
![]()
――ハード・スケジュールで、相変わらずいっぱいいっぱいな状況ですか?
「いっぱいいっぱいですね(笑)。もうね、なにを犠牲にしているかって、プライベート・タイムですよ」
――妥協せず、さまざまな表現活動に挑戦し続けるスタンスは昔から変わらないんですけど、なにがそうさせているんですか?
「性格かな。良くも悪くも完璧主義。悔いを残したくないっていう気持ちが強いってこともあるし」
――プライベートを充実させたいとは思わないんですか?
「“結婚しないんですか?”“将来設計は?”ってよく訊かれるんだけれども、40歳までは突っ走るって決めているので(ミッチーは現在39歳)。ただそれは、区切りとしてね」
――たぶん、40歳以降も突っ走っていると思うんですけど(笑)。
「うん、なんにも変わらないとは思うんだけどね(笑)。モノ作りってキリのないことだし、表現に百点満点はないし、なによりも人生を楽しみたいという思いが強いから。そのためのツールとしてビジネスがあり芸術があるっていう考えは、昔からずっと変わっていないんですよ。人生の後半戦にさしかかったところで、いくつもの夢を実現させてきたぼくだからこそ、次の夢にどう着手するのかはしっかり考えてみたいですね。ぼく、考えないと行動できないタイプだから。衝動的に動けない」
――では、今回の『RAINBOW-MAN』はどんな計算をして、どんなシナリオを作って完成させたんですか?
「最近は毎年、作品を発表するごとに、ツアーを展開するごとに、イメージ・カラーというものを決めていたんですね。それを今回はなしにして、一色に決めないってことは無色か七色かなっていうイメージがあって、じゃあ次のアルバムは虹にしようと。カラフルな内容にしようと。ぼくの持っている多面性を音で表現したいと思ったんですよ。ひとつのジャンルにとらわれない、コンセプトがないということを大切にして作ろうと思ったの。で、結果的に多面的で幕の内弁当的な、7曲入りのアルバムができあがったというわけなんだよね」
――もともとミッチーはいろんな表情を見せてきたアーティストなんですけれども。
「そうだよ。でも、あれもこれも食べたいっていう、お子様ランチの喜びが欲しくなって(笑)。アルバムでいうと2ndや3rdに近いノリかなあ……。それでトータリティのないぶん、聴きづらいものになるだろうっていうのはあったので、15曲も入れられないと」
――計算してる!
「だから、よく考えているんだって!(笑)」
――曲を聴く限り、ずいぶんとスムーズに作れたんじゃないのかなって感じたんですけれども。
「そう! だって1曲それぞれのことしか考えずに作っていったわけだから」
――しかも、どの曲も弾けまくっている。
「そうだね」
――弾けた曲ができあがったのは、制作方法が理由だけだとは思えないんですけど。
「遊びたいっていう気持ちじゃない? ほら、こう見えてぼくは、コツコツと、人さまにそういったトコロを見せない努力家……って、自分でいっちゃったけど(笑)、努力を惜しまないタイプなので、そんな生真面目さを緩和したいっていうのがあったのかな。閃いたことを、そのまま鮮度を保って形にできたらなと」
――経験値が邪魔したりしませんでした?
「創作意欲に忠実であろうとするぼくには大ヒット曲がないわけですよ(笑)。だから最初からファンに対して安心感を与えることがないというか……それは音楽的な意味でね。スターとしては期待には応えるけれども、つねに予定調和から逃げまくってきたから、“ミッチーの音楽はこのスタイルじゃなきゃ!”っていう決まりごとが、ぼくにはないと思うんだよね」
――予定調和から逃げながらも、たくさんいる熱心なファンにミッチーはどうやって向き合っていくんですか?
「人として、ですよ!」
――うはははははは!
「結果的にぼくの楽曲っていうのはライブでもって帰結するっていうか……ライブをより盛り上げるためのツールであるとは思いますね。ファンのみんなと一緒に踊ったり、掛け合いをしたりするのがぼくの喜びだし。ぼくは、ブログや日記のように、ひとりでなにかをコツコツ書いて満足を得るタイプじゃないんですよ。それをたとえるなら手紙であって、受け取ってくれる人がいて初めて意味を成すというか。そのあたりは、長年のファンとの交流のなかで、彼女ら、彼らが笑顔で喜んでくれるであろうという思いやりと、いまのぼくがこういうことに挑戦したいんだっていう意志を、サービスとエゴの調和でもって完結させますね。まあ、ミッチーって、踊ってなんぼでしょ?」
――『死んでもいい』がライブで一番盛り上がるのは曲の良さ以上に、ミッチーというパッケージングとして成立しているからだと思うんですよね。
「うん。ベイベーたちの参加意識を高め続けてきたからね! 踊る阿呆じゃないけど、踊らないほうが逆に恥ずかしくなる異空間を作り上げてきたというか(笑)」
――あの歌、歌詞はものすごく暗いのに(笑)。
「ぼくの曲は歌詞、暗いのばっかり……って、放っておいてよ!(笑)。でも、曲調は明るいのに歌詞が切ないって、とってもロマンティックで泣けて、いいと思うんだよね。笑いながら涙が出るっていうのは、人間の一番美しい顔だと思う」
――究極のエンタテインメントがいざなうものですよね。
「そうだね。自分でいうのも変だけど、ぼくのような生き方に誰が共感してくれると思います? ドラマに出演したって、頭がいいとか金持ちとかキザの役しかこないこのぼくに(笑)。世の男子諸君にとっては共感できる兄貴キャラではないわけで、人に疎ましがられる存在……って、子どものころからのことで慣れていますし、いまさら傷つきはしませんが(笑)、自分をパロディとしておもしろおかしく表現しなかったら、カチンとされる存在のまんまじゃないのかな」
――『RAINBOW-MAN』にはいままでと違う質のユーモアが感じられて、だからいまのミッチーは表現することに対して余裕があるのかな、と。
「昔に比べたらね。ミッチーというキャラクターを演じている、プロデュースしているっていう感覚かな」
――ミッチーには、自分自身に対する冷静な批評眼があるっていうことなんですよね。
「そうですよ。だってぼくがもしお笑い芸人目指していたら、狩野英孝になってますよ(笑)」