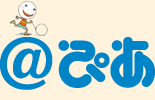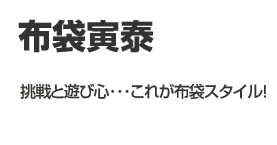- �wGUITARHYTHM V�x
- ������/3000�~
- EMI�~���[�W�b�N�E�W���p�� / TOCT-26795
���҂�TOP > �C���^�r���[ > �z�ܓБ�
![]()

�z�ܓБׂ̃j���[�E�A���o���̃^�C�g���́wGUITARHYTHM V�x�B�܂�͂���ȑO�ɁA4���́gGUITARHYTHM�h�����݂���킯�Ȃ̂����A���́gGUITARHYTHM�h�Ƃ͂��������Ȃ�Ȃ̂��B�z�܂ɂƂ��Ăǂ�ȈӖ�������i�Ȃ̂��B�gGUITARHYTHM�h�Ɋւ���x�[�V�b�N�Ȏ�����Ԃ��邱�Ƃŕ����яオ�����͔̂ނ̉��y�ɑ���O���Ȃ�����ƁA�V�[����s��ɑ����ÂȎ��_�ł������B
Text�����c �@�@Photo���O�R ��
![]()
�\�\�z�܂����1988�N�ɏ��߂Ẵ\���E�A���o���wGUITARHYTHM�x�\�����킯�ł����ǁA�ŏ��͂��낢��ƍl�����Ǝv����ł��B�o���h����ƈႤ���Ńr�b�N�������Ă�낤�Ƃ��A�ł�����ƃt�@���Ɉ����ꂿ�Ⴄ�Ƃ��c�c�B
�u�����Ȃ��A�O�҂������ˁB���܂܂ō�����X�^�C�����Ă݂�Ȃ��������Ă�낤�Ǝv���Ă��܂�������v
�\�\�����ł܂��A�R���s���[�^����g���ĉ������グ�Ă������킯�ł�����ǂ��B
�u(BO��WY��)����̃f���e�[�v�͂��������`�ō���Ă�������A�wGUITARHYTHM�x�̓f���e�[�v�̉����݂����Ȋ����ł����ˁB����ɁA�̂���f�B��r�����āA�T�E���h�E�N���G�C�^�[�Ƃ��Ă̎������m���������Ƃ����v���������āA�����ɁA(BO��WY��)���{��̃o���h�ɂȂ�������A���͐��E�Ƃ����A���̑���J���u�Ԃ������킯�ł���B�p��Ńg���C������A���{�̃`���[�g��V�[�������������������̂́A���������Ӗ�����������ł���ˁv
�\�\���̂��Ƃ��gGUITARHYTHM�h�Ɗ����ꂽ�A���o���������Ă����܂�����ˁB
�u�ɂ߂Ď��R�ɕω����Ă������Ǝv����ł���B���̂Ƃ����̂Ƃ��̎����ɒ����ɂˁv
�\�\���́gGUITARHYTHM�h�V���[�Y��������ƐU��Ԃ��Ăق�����ł�����ǂ��B
�u���ׂẴA���o���̂������Ƀ��C�u������킯�ł���B�܂��A�wGUITARHYTHM�x�o�������Ƃ́A���߂ăX�e�[�W�̐^�Ń}�C�N�ƌ��������ăI�[�f�B�G���X�ƌ��������āA�Ȃ��S�n�̈����������Ă�(��)�B�{�[�J���X�g���đ�ςȂȂƎv������A�o���h���Ă������̂��������Ȃ����肵�āB�ł�����Ȃ��Ƃ����Ă��Ȃ���ŁA���͂����ƁA���̃X�e�[�W���ӎ��������̂ɂ��悤�ƁB�����̒��ɂ��錶�z�I�ȁA���̍��X�|���Ă����V���[�����A���Y���̉e�����F�Z���o���̂��wGUITARHYTHM II�x(1991�N)�ŁA���̂��ƒ����c�A�[�ɏo����A�����Ɨ~���o�Ă����B�I�[�f�B�G���X�ɂ����Ƌ߂Â������A�����̋C�����������ƃX�g���[�g�ɒ����Ăق������Ƃ����C�����ō�����̂��wGUITARHYTHM III�x(1992�N)�B�����Ă܂��c�A�[�ɏo����A�ꏏ�ɉ�����o���h�E�����o�[�Ƃ̖��ڂȊW���ƂĂ��S�n�悭�v�����̂ŁA�wGUITARHYTHM IV�x(1994�N)�̓o���h�E�T�E���h�ł������Ɓv
�\�\���́wGUITARHYTHM �W�x�ŁgGUITARHYTHM�h�V���[�Y���I���������̂͂ǂ����ĂȂ�ł����H
�u�����f�B�����t���A�����Ȃɂ��������ׂĂ��z���ȏ�ɖc���ł������̂ŁA����͂����gGUITARHYTHM�h�ƌĂԕK�v�͂Ȃ��Ǝv�����B�gGUITARHYTHM�h�����X�����������ȃR���Z�v�g�ŃX�^�[�g�������Ƃ�����A�����������Ȃ����Ă����̂ƁA�ЂƋ��������Ǝv���āB�����炻�̂��Ƃ͐V��������c�c�����ł��������炢�×~�Ƀq�b�g�E�`���[�g�̃i���o�[�P��_���Ă݂���A�����ƍ�肽���Ǝv���Ă����T�E���h�g���b�N���肪���Ă݂���A�R�}�[�V������f��ɏo����A�M�^���X�g�������畁�ʂ͂��Ȃ��Ă��������Ƃɒ��킵�Ă������B�����݂̂Ȃ��m��z�ܓБׂƂ́A�����炭�A����15�N��(1994�N���猻��)�̊������Ǝv����ł���v
�\�\�M�^�[�E�q�[���[�A���邢�͌Z�M�I���݂ɂȂ��Ă������̂����̎����ł����A�����v���Ă���͖̂{�l�Ƃ��Ă͂ǂ��Ȃ�ł����H
�u����܂苏�S�n�����Ƃ͎v��Ȃ�(��)�B���������C���[�W�����Ԉ�ʂɂ���̂͂킩��Ȃ��ł��Ȃ��B�����ǂق�Ƃ̎����͕��ς��ŁA���}���`�X�g�ŁA�t�@�b�V�����������A�����Đl�����ɂ܂��̂��D���Ȃ����Ɏ₵���艮���Ă����l�Ԃ�����A�Z�M�̂Ђƌ������Ō����Ƃ��Ȃ�Ⴄ��ˁv
�\�\�����Ȑl�����Ƃ̃R���{���[�V�����������Ă����̂��A����15�N�Ԃ̂��Ƃł�����ˁB
�u�l�t�����������܂��Ȃ��Ă�������(��)�v
�\�\�wGUITARHYTHM V�x�������Ȑl�������Q�����Ă����ł�����ǂ��B
�u�v���C���[�Ƃ������́A�g���b�N�E���C�J�[�A���Y���E���C�J�[�ADJ���Ă����l�������ł���ˁB�����̃r�[�g�������ƕ肪�������A�Ⴄ�r�[�g�ŃM�^�[��e���̂͐V�N���ȂƎv������ˁB��������A���̍�(�Pst�𐧍삵�Ă�������)�̋C���ɋ߂����̂������āA�V�����X�^�C���̃T�E���h�����߂鎩���ɖ߂肽���Ȃ��Ďv������ˁB�gGUITARHYTHM�h���Ă��̂��A���������R�ɂ����Ă���邱�ƂɋC�Â����B���Ƃ��Ƃ́gGUITARHYTHM�h���Ă����^�C�g����t�����A���o���ɂ�����肶��Ȃ������v
�\�\�V������������A�����ɑ���V�ѐS����������A���o���ł���ˁB
�u���b�N�ɒ��ނƂ������c�c�ق�Ƃ͂ˁA�������Ȃɂ���肽���̂����킩��Ȃ���ł���B�����犴�o�I�ɁA�������炱�ڂ�Ă�����̂����ɂ��Ă���킯�ŁA������t�@����X�i�[�͂ǂ�������̂��B�����I�Ȃ��Ƃ����Ȃ��牰�a�ɂȂ鎩����������ǁA���̎הO���N���G�C�e�B�u�̃p���[�ɂ��Ȃ��ł���B�G���^�e�C�������g�Ƃ����Ă����낢�날�邯�ǁA�����I�ł���Ȃ�����|�s�������e�B�ɔw���������A�P�����̂����B���ꂪ�ڂ��ɂƂ��ẴG���^�e�C�������g�B���̋P�����A�t�@���ȊO�̐l�������ڂ��̉��y�����������ɂ��Ȃ邵�A�l��x�点�Ċy���܂��邱�Ƃɂ��Ȃ�Ǝv������ˁv
���W�u�z�ܓБׁ@�M�^���Y�������ł݂邱�ꂼ�z�܃X�^�C���I�v