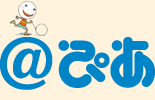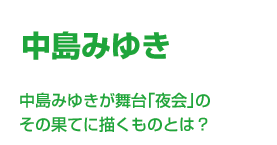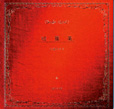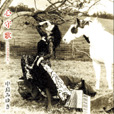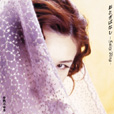![]()

中島みゆきが1989年にスタートさせた「夜会」の15回目となる公演が始まった。 コンサートとも違う芝居とも違う「夜会」に、中島はどんな想いをこめているのか?
Text●田家秀樹
![]()
“みゆきの歌に手が届く――”
中島みゆきがそんなキャッチコピーで「夜会」をはじめたのは1989年だった。演出・脚本・主演などの全てをひとりで行い、通常のコンサートホールとは違う小空間で約1ヵ月にわたるロングラン公演。それは世界でも例のない舞台表現だろう。
すでに世に出ている曲を違う物語の中に置き換えることで解放する。回を重ねるごとに新しい試みが加わり、7回目の「2/2」からは、全曲が書き下ろしになった。コンサートでも演劇でもない言葉の実験劇場。10回目の「ウィンター・ガーデン」は朗読劇だった。
11月20日から「VOL.15〜夜物語〜元祖・今晩屋」が始まっている。会場も今年から赤坂アクトシアターに移った。すでに会場に足を運んだ人は気づいているだろうが、毎回、赤だった公演パンフレットの色まで違う。

「気分も新たに、というところでしょうか。15回という区切りというわけじゃないんですけど、会場も変わることですし内容も真正面から“和”ですからね。元々「夜会」は非常にジャンルが分からないところで始まってるんですが、今回、音楽劇に立ち返ろうと。台詞と台詞の合間に曲を入れ込んでゆくというよりは曲から曲へ、歌詞で繋いでゆくという形なんですね。音楽の中にストーリーが全部入っている。方向としてはミュージカルというよりオペラでしょうね。だもんですから、今回は、曲、多いよ(笑)」
「〜夜物語〜元祖・今晩屋」は、森鴎外の名作としても知られる「山椒大夫」がモチーフになっている。誰もが知っている“安寿と厨子王”の物語である。
前回の「24時着0時発」では、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を下地に“命のリレー”というテーマの新しい物語を生み出していた。
「今回、「夜会」というものを自分に引きつけようと強く思ったんですよ。自分の価値観みたいなものを掘り下げてゆくと、こういうものに当たっちゃうんですね。中島丸出し(笑)。あのお話は子供の頃から何度読み返しても「え、何で」と思うことがたくさんあってずっと気になっていたんです。その年代なりの「何で」という疑問が積み重なってきたんで、ホールも変わるし、ちょっとは新しいことも出来るかもしれないということでこれにしました」
「山椒大夫」は、父親に会いに行く途中に人買いに売られ、自分の命を投げ出して弟を逃がした姉と、生き延びて成長し生き別れになった母親を捜す弟が織りなす家族悲話だ。
とは言うものの、新たに読み直すと、子供の頃には気づかなかった別の何かが読み込まれていると思う人も多いはずだ。
「おとぎ話ってそういうものじゃないかしら。何十年、何百年と経つうちにどうとでもお取り下さいというものになってゆく。謎が一杯隠してある物語だと思うんですね。解こうとするとその人の本質に関わってくる恐ろしいお話かもしれませんよ」
それは例えば、どういう疑問だったのだろうか。
「一番最初にひっかかったのは、お母さんがなんであんなに簡単に騙されるんだろうということ。その次が、お姉さんと弟の気持ちですね。“待ってるから”と言って弟を逃がして水に飛び込んだお姉さんは美談で、弟はお姉さんを犠牲にして生き延びたということをずっと引きずるわけですね。弟にすれば“待ってる”と言うのは嘘であり裏切りでもあるんですよ。でも、それを裏切りと言ってしまっていいものなのかどうか。そういう歌もあります(笑)」

“やさしき者ほど傷つく浮世
涙の輪廻が来生を迷う
垣衣(しのぶぐさ)から萱草(わすれぐさ)
裏切り前の1日へ
誓いを戻せ除夜の鐘”
公演ポスターにはそんな歌詞の一節が載っている。
彼女は「今回は歌も台詞も七五調なんです」と言った。
「不思議な感じよ(笑)。リアルなようなリアルじゃないような。でも、七五調というのは万葉の昔からですから、日本人の発音の根本に関わっているものなんでしょうし、韻が乗りやすいんじゃないでしょうか。自分の中にあるものを突き詰めると七五寄りなんだと思いますよ」
振り返ってみれば、70年代に登場したフォークソングは歌の言葉の革命だった。
文語調などの形態に捕らわれない平易で自由な日本語。それは従来の歌謡曲とは明らかに違うリズムを持っていた。彼女もそういう流れの中で語られることが多かった。
「でもね、私、学生の頃、“七五の人”って呼ばれてたの。英詩を訳する時に、普通の散文や会話文T同じような日本語にするのが嫌だったのね。英詩を“和”で表現するとしたら何だろうと思って七五で訳したんですよ。そしたら全員爆笑なさいましたけど、次の回から先生に“七五の人、今日はやってくれないのか”って(笑)。高校の音楽の時間に自分で書いた曲を提出しなさいっていう時も七五で歌詞をつけましたからね。それも爆笑されましたけど。それを今に引きずり込んで行くとそこにはまってゆくんですね。安寿と厨子王が、私をそこに引き戻しましたね。ただ、台詞もそうですから、役者さんたちはイントネーションとか、どこで切るのかとか、大変に戸惑っていらっしゃいました(笑)」
中島みゆきの原点――。
七五調が、言葉のリズムとスタイルという意味でそうだとしたら、公演ポスターに並んだいくつかの言葉も彼女がデビュー以来歌ってきたテーマでもあるのではないだろうか。
“やさしき者ほど傷つく浮世”、である。
志半ばで傷つき倒れた旅人たち、愛する人に裏切られ我が身を嘆く女性たち。思うように生きられずに人知れぬ涙を流してきた人たちにとって、中島みゆきの歌はずっと駆け込み寺のようなものだったのかもしれない。
「元祖・今晩屋」――。
そのタイトルに込めたものは何だったのだろうか。
「最初に浮かんだのが、そういう歌もあるんですけど“夜いらんかいね”だったんですね。そこから引っ張られていった。安寿さんと厨子王さんもそうでしょうけど、もしあの一晩があったなら、と思っている人は多いと思うんです。そういう方に、夜をお売りしたいなと。春を売るんじゃないのよ(笑)。でも、人間としての本質的なセンチメンタルの究極じゃないでしょうか。安寿も厨子王も千年以上も繰り返しくるしんできたんでしょうから。みんなもう苦しまなくていいよ、と最後に分かってもらえればという物語ですからね。安らかに成仏してグッズを買ってお帰りいただければと思います(笑)」
彼女は昨年の本誌(10月4日)号での特集「100の質問」の中で、「理想とするのは大衆演劇」と答えていた。
それはどういう意味だったのだろうか。
「大衆演劇と言った時に想定したのは、演劇論で語られて、優劣をつけられるというところは目指していないということでしょう。そういうことをありがたいと思ったりするよりも、今、面白ければいいじゃんというか。やんややんやという。演劇論として何が高尚か、みたいなところには居たくないということで言ったんでしょうね」
つまり「夜会」も、大衆演劇ということなのだろうか、そして、今後もそこを目指してゆくことになるのだろうか。
「そうなって行ければと思いますね。それこそ仕事場やお宅とかで色々大変なことがある方たちにお金を払っていただいてる訳ですし。コンサートでも言いましたけど、ちょっとの間、荷物を降ろして深呼吸してもらえればそれで良いと思うんです。それに対して論じられるのは人様の自由ですけど、これだけのことをやってるんだからすごいのよ、みたいな論は必要ないということでしょうか。大阪の方たちが使う、“おもろうてやがて哀しき”、ですか、ああいうことで良いんだと思いますね。ただ、やればやるほど答えは出ませんけど。今回も全部覚えるの難儀よう(笑)」
元祖・今晩屋――。
それは彼女自身のことでもあるのかもしれない。